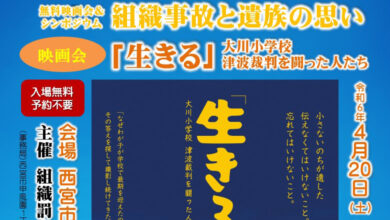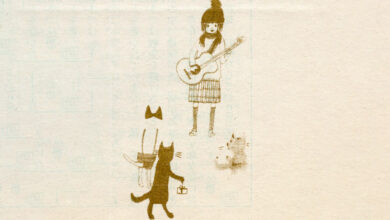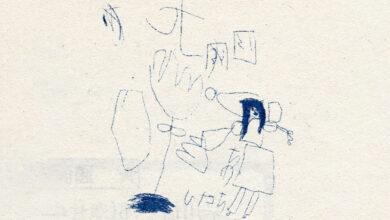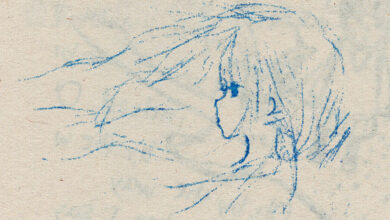障害者•高齢者が地域社会で自分らしく安心して暮らすために

弁護士 青木佳史
「僕は生活上のあたりまえのことをさっぱりわかっていませんでした。53年間生きてきて、今さらそんなことがわかったとは驚きでした。本当にいろんなことを一気に学んでしまいました。地域に出ていくと、洗剤•水の使い方、電気の使い方、それらを含めた経済観念が必要です。それから地域で共同で生活するのに必要なこと、たとえば階段を下りるときの足音、ドアの開け閉めのこと。そして人との交流。たとえば、「こんにちは」との人との会話。なぜ必要かというと地域で暮らしているからです。入所施設では教えてくれなかったことです。」
「それからくれぐれも、A君とB君を一緒にするなということです。A君にできてもB君にできないことも当たり前。B君には常識でも、A君にはわからないこともあります。A君とB君を一緒にするのは入所施設独特のことです。」
「これから私はどんどんつまづくでしょう。しかし僕は生きたいと思います。私はいろいろなことを身体で体験させていただきました。それが私にとっては大きな喜びです。」
これは、35年間入所施設で生活をしてきた53歳の知的障害のある男性が、施設を出て、地域のグループホームでの生活を始めて感じた痛切な想いを綴ったものである(『もう施設には帰らない─知的障害のある21人の声─』<中央法規>より)。「入所施設は現実を教えない」「1人ひとり違う生き方を教えない」との鋭い問題提起を、私たちはどう受け止め、何を変えていかなければならないのでしょうか。
わが国の福祉政策は、2000年4月から介護保険制度が実施され、2003年4月には障害者福祉に支援費制度が実施されました。2005年には、介護保険法の全面改正が予定され、また介護保険制度と支援費制度の統合が大問題になっています。支援費制度の下、障害者福祉施策を地域生活を中心に進めることが打ち出され、介護保険法の見直しにおいても、『2015年プラン』では高齢者を住み慣れた地域に近い環境で支援をしていく方向性が示されています。さらに、精神障害者についても、35万人と言われる長期入院者の地域生活への移行について、ようやく本格的な施策を講じる動きが出てきました。今、福祉をとりまく環境は大きく変化しようとしています。
しかしながら、新しい制度導入で福祉サービスの利用が急速に伸びた結果、予測されたことであるにもかかわらず、福祉財政が圧迫されるとして、厚生労働省や国会では、介護保険料の徴収範囲の拡大、これを含めた支援費と介護保険の統合が大きな焦点になり、利用者負担の増大や受給できるサービス量の低下などの危惧が大きく広がっています。
しかも、地域で安心して自分らしく生活するということは、様々な社会生活上の困難をかかえた高齢者•障害者にとって容易なことではありません。入所施設や病院の「保護」された空間での生活に比べ、たくさんのリスクがあります。
実際に、「地域で暮らす」との名目で急増した痴呆性高齢者対応のグループホームの中には、先日起きた北陸での事件ばかりでなく、劣悪なサービスや管理体制のものが多数指摘されており、サービスの質の確保が緊急の課題になっています。
また、高齢者•障害者虐待も深刻で、昨年度実施された厚生労働省の初の全国調査では、在宅における高齢者虐待の深刻な実態が明らかになり、これに対する支援策が早急に求められています。知的障害者の就労現場における虐待事案も、私も弁護団として取り組んだ滋賀•サン•グループ事件訴訟で、これを放置した福祉行政に対する厳しい国家賠償責任が認められましたが、その後も大きな改善策はとられないままです。
近時、認知症高齢者や知的障害者や精神障害者に対する悪徳消費者被害は急増し、大きな社会問題となっており(『痴呆性高齢者•知的障害者への消費者被害の研究』(国民生活センター編))、相談体制の整備とともに、成年後見制度等や地域での見守りなどの対応が求められています。
また、先の新潟中越震災、そして阪神大震災においても、多くの要介護高齢者のサービスが途絶えたり、知的障害者の作業所やグループホームの廃止の危機などが露呈し、災害時に最も深刻な影響を受けるのが高齢者•障害者であり、これに対する無策が浮き彫りになりました。
地域で、普通に安心して暮らすことは、誰にとっても当然の基本的人権である、との確かな理念のもとで、当事者である障害者や高齢者自身のニーズと自己決定に基づき、これを支える社会福祉サービス等の整備と権利擁護のための支援策、そして地域社会の理解と共同がなければ、「地域で暮らす」ことは「理念」に終わってしまいます。
社会福祉基礎構造改革のもと、誰もが自分らしく安心して地域で暮らすことを理念として、契約型福祉社会がスタートして5年。今こそ、あらためてわが国の福祉施策のあり方を正面から見直す時期が来ています。年老いても、障害があっても、地域で共同した生活を送ることのかけがえのなさは、前述の手記が、私たちに鋭く投げかけている課題です。それを、この先、私たちの社会が、本気で実現していくのかが問われています。
日弁連は、今年の11月10日、鳥取県で開催される人権擁護大会で、「いつまでもこの地域で暮らしたい─高齢者、障がいのある人が地域で自分らしく安心して暮らすために」というテーマでシンポジウムを開き、岐路にたつ障害者•高齢者福祉のあり方を、ひいてはわが国の社会としてのありようを、財源論やサービス提供者の論理ではなく、障害者や高齢者の「当事者主権」の確立の視点から、政策と実践の提言を行うことにしています。私は、そのシンポジウム実行委員会の事務局長として、今、各地の実践に学び、準備とまとめに忙しくしているところです。
 もう施設には帰らない─知的障害のある21人の声─
もう施設には帰らない─知的障害のある21人の声─
10万人のためのグループホームを!実行委(編集) / 中央法規出版 / 2002年12月1日
<内容>
日本には入所施設で暮らしている知的障害者が約12万人いる。多くの親が自分が死んだ後の不安から入所施設を望み、行政もそれに応えてきた。しかし本人たちの気持ちはどうなのだろう。知的障害のある21人の声を収める。
 介護事故とリスクマネジメント
介護事故とリスクマネジメント
高野範城(著), 青木佳史(著) / あけび書房 / 2004年11月1日
<内容>
介護サービスを安心して実施するための考え方と手だてを多くの介護事故例•裁判例から具体的に記す。法律家と事業者•実務家による画期的集団労作。介護事故だけでなく、損害賠償保険の適切な活用法、財務会計管理におけるリスクマネジメントにも論及。裁判例を集め、分析した巻末資料編は貴重。介護事業者•従事者、法律専門家必携の書!
青木弁護士も高塚門扉裁判の最初から担当してくださった弁護士です。それぞれの立場から今、一番関心のあることや取り組んでおられることを書いていただきました。どれもこれも大切なことばかりで、皆様是非隅から隅まで読み落とすことの無いように読んでください。