定時制高校 青春の短歌 (生きた証し)
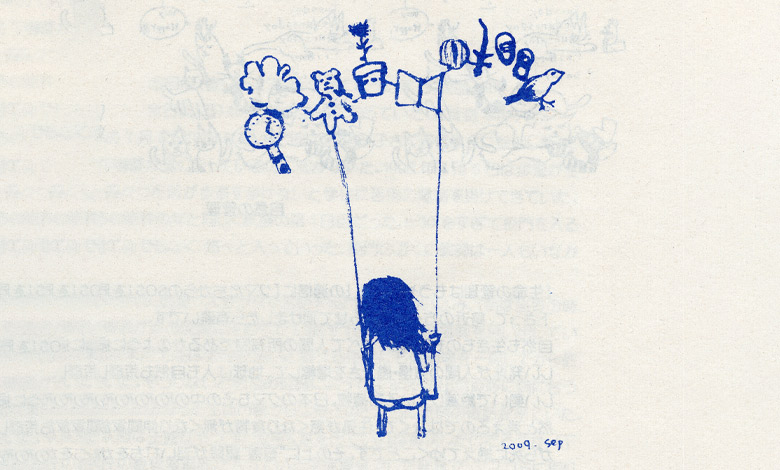
神戸工業高校 南悟
生きた証し
盲目の私自身に今はもう何も残らず未来は無い
人なんて結局自分が大切で私の友は安定剤 麻里 (2009年) 仮名
麻里さんは、昨年の暮れにやむなく退学しました。退学後も定期的に連絡は取っていましたが、生きることの難しい生徒です。今年の六月に久しぶりに学校へ私を訪ねてくれ、その夜は元の級友宅に泊まる約束があったようです。
級友の授業が終わるのを待つ間、私の机の横に座り、読書をしたり、メールを打ったりしながら、この短歌を作りました。一読して、彼女の充たされない心の飢えを感じさせられる歌です。「私が生きていた証拠やからね」。「そうかあ、まだまだしんどいなあ。けど、また、ここから始めようなあ」という私の問いかけには無言でした。
彼女もまた、腕を切り、安定剤が手放せませんでした。入学以来、学校には来ていましたが、四月の終わり頃から、家出をしたままの生活でした。毎日学校へは来ていたのです。自宅へ帰るように話し合いましたが、解決には至りませんでした。
夏休み、彼女は私の家で三週間過ごしました。彼女との出会いは深夜の公園です。「迎えに来て欲しい」という電話で駆けつけると、ベンチにうずくまり両方の腕が血まみれでした。その光景に、胸が潰れる思いがし、暗澹とした気持ちになりました。お母さんに、私の家で預かっていると連絡を入れると安心されていました。三ヶ月も家出をしていた彼女は見るからに疲れた様子で、世話になっている人とは喧嘩別れをしたので行き場がないというのです。自宅へ連れ帰ろうとしましたが、それなら家出をすると決意していました。
中学二年生頃から、情緒不安定でリストカットを繰り返し、入院歴もあって安定剤を服用していました。彼女の世話のために、共働きのお母さんは仕事を辞めておられました。
定時制高校に入学して、お洒落な彼女は三宮のイタリアンレストランで働き始めました。仕事も学校も順調で両親が少し安心されたのもつかの間の家出でした。
ガラス細工のように繊細な感性で、孤独で他人を寄せ付けない雰囲気の彼女も、我が家では、徐々に穏やかになっていき、家庭料理と家族の団欒を喜んでくれました。妻とは、買い物に出かけ、夕食の準備を共にこなし、海辺や川沿いを散歩して過ごしました。私には話さない彼の話も、いろいろと相談していたようです。生活の端々から彼女の優しさをうかがい知ることが出来ました。落ち着いてからは、腕を切らなくて済み、安定剤も飲まなくて済んでいたのです。
ピアノを弾くことが好きで、サティのジムノペディなど聞かせてくれました。椎名林檎の音楽を聴くことも、読書も絵を描くことも好きな、芸術とファッションセンスが豊かな少女です。ただ、一六才になったばかりの少女が、シャンソン歌手ダミアが歌う「暗い日曜日」を聞き込んでいることが不思議に思えました。
二学期からの生活設計として、自宅に帰れない理由も理解できたので、彼女の独立生活を考えていく事になりました。両親とも相談して、学校の近くのワンルームマンションを探しましたが、一六才の女生徒の部屋探しは難渋しました。あちこち駆け回り、五~六軒目でやっと借りられました。お母さんの目が届く距離です。
独立の生活資金として、神戸の市民グループ「高塚門扉」の皆さんからのカンパも活用させていただきました。石田僚子さんの死を伝えると、言葉数の少ない彼女も「そんなん殺人やんか」と怒りに震えていました。見知らぬ人たちが、あなたを見守っているのだから生きていくようにという私の言葉に「わかった」とうなずいてくれていました。アートスペースかおるの「紙芝居」も楽しかったと感想を述べていたのです。
独立生活を喜び、仕事はお好み焼き店に勤めましたが、生活のために、祖母の営む夜の飲食店にも週のうち二~三日手伝いに出るようになりました。学校から徐々に足が遠のいていきましたが、慣れない独立生活を維持するのが優先で、私もいずれ戻ればいいだろうと判断したのです。
時おりの電話とメールで近況を知り、またお母さんからの情報でなんとか元気にしているとのことで少しの安心は得ていました。冬の二月に学校へ訪ねてくれた時も、これまでの彼女とはずいぶん違って爽やかな表情が見てとれ、春から学校へ戻る話も出たほどでした。
春からの学校はあと一年先延ばしになりました。次に訪ねてくれたのが、この短歌を詠んだ時です。
多量の安定剤を持っているのが気がかりでした。別れ際、また落ち着いて話し合おうという私に「ありがとう」と言ってくれたのです。
それから、わずか二週間後、自らの手で命の火をかき消してしまったのです。
お母さんや友だちから、二~三日も連絡が取れないと慌てた様子で電話があって、私にも不安がよぎりました。その不安を抱いた夜の出来事です。
取り返しがつかないことをしてしまった後悔と、助けられなかった悔しさで、打ちのめされました。家族の悲しみはもちろんのこと、彼女に関わった誰もが喪失感は大きく、後悔の念にさいなまれました。
この六月、一七才になったばかりです。なぜなのだ、どうして死ななければならないのだ、生きていた証拠の短歌など要らない、あの時ああしておけば良かった、こうしておけば良かった、と考えが堂々巡りするばかりです。
亡くなる三日前にもメールで詩が届いていました。
••••
••••
••••
••••
結局生きていくすべは
全て自分自身にある
純粋では生きれない世界
仮面では生きれない世界
他人のせいにして
結局は自分のせいなのに
ごめんなさいごめんなさいごめんなさい
結局のところ
自分が世界を潰している
もう終わりね、ベイビー
彼女から電話があったので、「生きていてほしい」と伝えましたが、思いは届きませんでした。お別れの火葬場で、白い小さな遺骨を拾い上げながら、とめどなく涙があふれ出て止まりませんでした。
彼女が亡くなった後、安定剤や抗うつ剤のような薬物には、死を誘発させる副作用があって、常用すると危険であることを知りました。そして、ダミアの「暗い日曜日」に込められた、中学校2年生の彼女を襲った日曜日の忌まわしい事件も。それから情緒不安定に陥ったことも。
知らなかったばかりに、彼女を支えることが出来なかった私は、自分を責め続けています。
Damia – Sombre dimanche
 生きていくための短歌 (岩波ジュニア新書 642)
生きていくための短歌 (岩波ジュニア新書 642)
南悟(著) / 岩波書店 / 2009年11月21日
<内容>
昼間働き夜学ぶ、定時制高校の生徒たちが指折り数えて詠いあげた31文字。技巧も飾りもない、ありのままの思いがこめられている。働く充実感と辛さ、生きる喜びと悲しみ、そして自分の無力への嘆き。生き難い環境の中で、それでも生き続けようとする者たちの青春の短歌。
 ニッカボッカの歌: 定時制高校の青春
ニッカボッカの歌: 定時制高校の青春
南悟(著) / 解放出版社 / 2000年5月1日
<内容>
失敗や挫折や障害が癒され、人として生きる力が与えられる定時制高校の生徒たちの短歌、作文を紹介。NHKドキュメンタリー番組で放映。
 定時制高校青春の歌 (岩波ブックレット NO.351)
定時制高校青春の歌 (岩波ブックレット NO.351)
南悟(著) / 岩波書店 / 1994年7月20日
<内容>
「大阪で道路舗装し夕映えの神戸の夜学に車を飛ばす」毎日、汗と油にまみれて働きながら、通学する夜間定時制高校の生徒たち。短歌に詠みこまれた喜び、悲しみ、悔しさ、そして恋─青春いっぱいの姿を教師が綴る。









