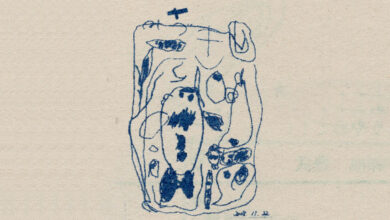率直になれない私たち
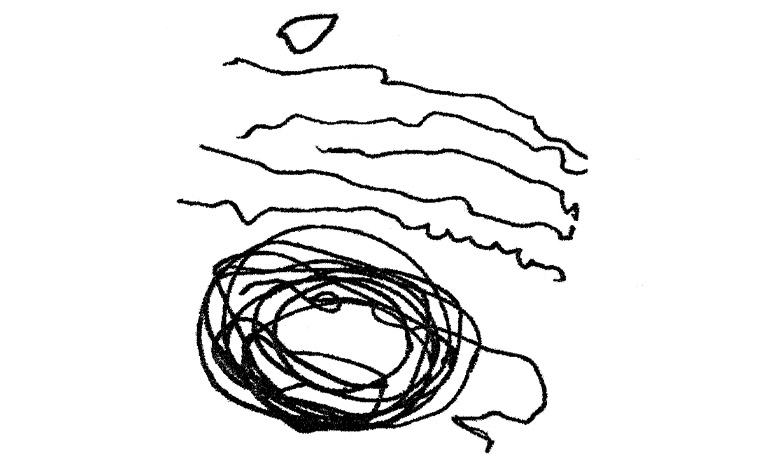
弁護士 峯本耕治
児童虐待による死亡事件が連日のように報道されています。10年前には考えられなかったことで、児童虐待問題への社会的関心が、この数年、驚くほど高まっています。この熱気が冷めないうちに、きちんとした体制や制度を整備していきたいものです。
ところで、ご存知の方が多いと思いますが、この児童虐待問題への取組において中心的な役割を果たしているのが、児童相談所のソーシャルワーカー(「SW」)です。このSWが、虐待を発見した人や機関から連絡(通告と言います)を受けて、虐待の調査が開始されるわけですが、その出発点になるのが、通常、SWによる家庭訪問です。この最初の家庭訪問の際に、SWは、親に対してどういう説明をすると思いますか?実は、この最初の説明の仕方に、日本のSWとイギリスのSWとでは大きな違いがあります。この違いは、日本とイギリスの文化の違いとも言えるもので、なかなか面白いものです。
日本のSWは、通常、虐待の通告があったことを隠した上で、当たり障りのない理由をつけて、子どもや家庭の状況を聞き出そうとします。「虐待の通告に基づいて調査に来た」などといえば、それだけで、親から激しい反発が返ってきて信頼関係を築けず、その後のケースワークがしにくくなると考えるからです。私達にとっては、大変、理解しやすい心情です。確かに、はっきり言わない方が、その場の混乱や反発は小さくて済みます。しかし、その反面、虐待の疑いを持っていることを言えないため、本質的な質問ができなかったり、いつまでも虐待の存在を前提とするアクション(たとえば、明確な指導や法的手続き)をとれないという問題が生じることが少なくありません。
これに対し、イギリスのSWのアプローチは全く異なっています。最初から、「虐待の通告があったので、その調査のために来ました」ということを率直に説明するのです。それは、SWにとっては大変しんどいことで、時には親からの激しい反発や抵抗もあります。しかし、そのような反発や抵抗があったとしても、SWは、「調査への協力が得られなければ、法的な手続きを取る可能性があること」と共に、「子どもを奪ったり、罰したりするために来たのではなく、子どもや家族に対して支援することを目的としている」ことを説明し、調査への協力をストレートに求めていきます。そうすることによって、明確な姿勢で親に関わっていくことができ、本当の意味での信頼関係を築くことができると考えられているわけです。
イギリスの児童虐待防止制度の基本理念の一つに、親とのパートナーシップがあります。このパートナーシップの意味について、友人のSWに尋ねたところ、次のような回答が返ってきました。
「SWは、最初から正直•率直な態度で親と接しないといけない。虐待の疑いを持った場合には、そのことを隠さないで、最初から、虐待の不安を感じたので訪問したと、きちんと説明しなければならない。それに対して、激しい怒りや反発を示す親もいるが、重要なことは、同じ困難に直面するなら、最初(早い段階)に困難に直面しておかなければならないということである。困難への直面を先延ばしにすると、親の不信感などを招き、困難が一層大きくなる。率直に説明した上で、その後の手続きの説明をきちんと行い、子ども保護会議(ケース会議)に提出するレポートを事前に親に渡すなどの情報提供を十分に行い、会議への参加を保障し、意見をいう機会を十分に保証すること等によって、親の納得と協力を得る努力をしていく必要がある。それが、親とのパートナーシップの内容である」
この回答を聞いて、大変感心しましたが、わたしたち日本人は、どうしても、目先の困難や混乱、衝突を避けることを優先してしまい、このような率直さを持てない傾向があります。「本音と建前の文化」も、このような率直になれない傾向と密接に関係しているように思います。
そして、このような傾向は、身の回りの小さな人間関係から、政治のレベルまで、実に様々な問題や弊害を引き起こしています。
私が弁護士として扱っている事件の中にも、自分の気持ちや主張を率直に言わなかったために、ボタンを掛け違ってしまい、大きな揉め事に発展したというケースが珍しくありません。
行政や政治のレベルでは、事はもっと深刻です。いくらでも例を挙げることができますが、たとえば、現在、福祉分野では、福祉施設等への入所に関する「措置」制度を廃止して、入所者(保護者)と施設との「契約」制度に切り替えていこうという動きが出てきています。厚生省は、その切替の趣旨として、契約制度の導入によって市場原理が働くようになり、利用者へのサービスが向上することになる等の説明を行っています。しかし、多くの福祉関係者が感じているように、この切替の主たる目的は、行政が責任を担う「措置」制度を廃止することによって、行政の責任を小さくし、予算をカットすることにあります。つまり、「建前」は契約制度の導入によるサービスの向上ですが、「本音」は予算の削減にあるわけです。多くの関係者は、その「本音」に気づいているわけですが、何故か、誰も正面から、そのことを議論しようとしません。学者も、「建前」に乗っかった議論を繰り返しているだけです。このような建前に基づく、形式的な議論をしているだけでは、結局、予算がカットされるだけで、契約制度が持つメリットが発揮される制度とはならないで終わってしまいます。「本音」が予算のカット、つまり、予算がないという点にあるならば、正面から、「予算がないので、予算を抑えたままで、サービスの質を維持•向上させる方法はないのか」という率直な問題提起をすべきです。そうすることによって、はじめて、本質的な議論が行われるようになり、現実的で、合理的な制度を作り上げていくことができます。
今の日本の政治を見ていると、同じような形式的な議論や建前に基づく議論がいたるところに蔓延しています。それが現在の日本の閉塞感の原因となっています。小泉首相が80%を超える異常な支持を得ているのは、そういう中で、少しでも「本音」と「率直さ」を感じさせてくれるからだと思います。ただ、そうは言っても、民主主義の下では、法改正を必要とする本質的な制度改革のためには、政党として動ける体制が絶対に必要なので、論理的に考えて、大きな改革は期待できないでしょうが。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。
Sponsored Link