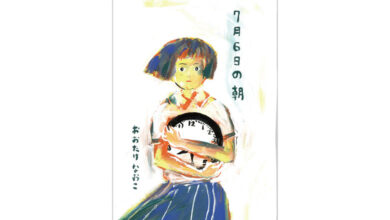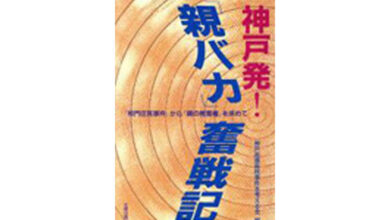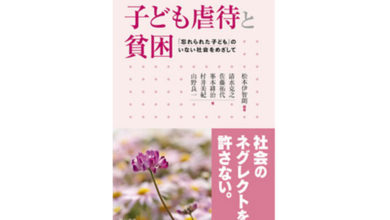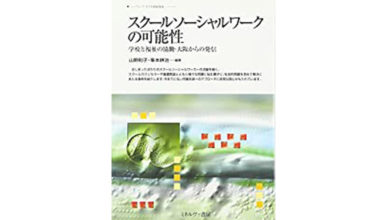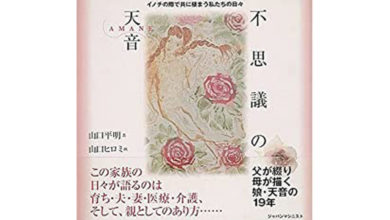『それでも少年を罰しますか』
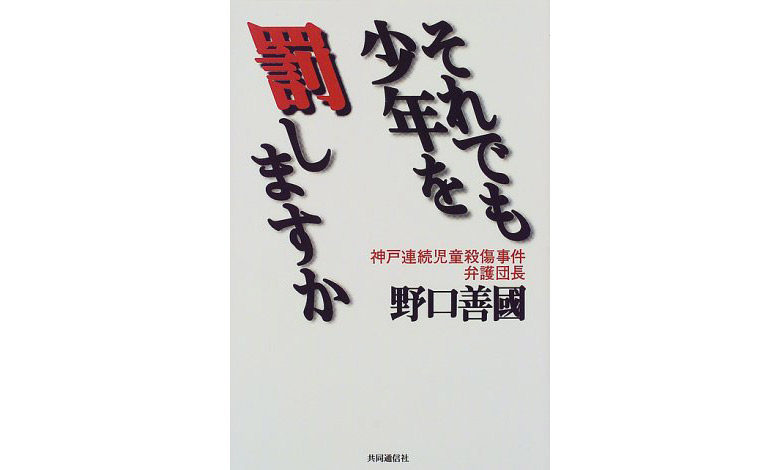
野口 善國 (著) 共同通信社 1998年刊
少年法「改正」は必要か 「透明な存在」からのSOS
少年Aは特異な存在か?担当弁護士が初めて明かす少年の実像。厳罰化を推進する少年法「改正」は非行防止につながらないと批判する
「私には非行の陰には大人に対し助けを求める子どもの悲鳴が隠されている気がしてならない。この悲鳴に耳を傾けようとせず、いたずらに厳罰をもって子どもを威嚇して非行を減少させようとすることは長期的に見れば事態をより悪化させることになろう。
本文より
別件で付添人を引き受けたY君はたまたまX君と同じ中学であった。Y君は教師に殴られて鼻骨を骨折したが、学校からは正式な謝罪もされず、教師には何の処分もなかったようである。生徒が教師に暴力をふるえば表沙汰になり、その逆はうやむやになることが多い。
1998年9月、神戸市は過去5年間に発生した教師による体罰の処分結果76件を文部省に報告していないのではないかとマスコミが報道した。神戸市が体罰を容認しているわけではないが、全国的に見て教師の暴力が「愛のムチ」の美名のもとに、熱心さのあまりの指導の行き過ぎとして、情状酌量されすぎる傾向がある。
1992年にロサンゼルスに行ったときに聞いた話である。日本の高校生が修学旅行でロサンゼルスに行った。ホテルでの集合に遅れた生徒がいて、引率の教師がその頰をたたいた。すると直ちに警察に通報され、教師は警察に連行されてしまった。教育には一定の厳しさやしつけは必要であるが、それが暴力によって行われることは許されない。
家庭でも十分な愛情を与えられなかった子どもたちが、学校でも人間性を否定される仕打ちを受けたとしたら、自分に対する誇りや他人に対する思いやりを持てなくなってしまうのではなかろうか。
管理主義教育
神戸市は古くから外国貿易でにぎわった港町であり、ハイカラで自由な雰囲気の都市と思われている。しかし、遅刻を防止しようとして生徒の命を奪う結果になった市内女子高生の校門圧死事件はあまりにも有名になってしまった。また、政令指定都市では一番最後まで(つい数年前まで)市立中学生に丸刈りの強制をしていたのも神戸市である。
(中略)
それは私たち国民のプライバシーが守られなければならないのと同じである。
被害者側のプライバシーが侵害されているから、少年側のプライバシーを侵害してよいというのは、誤ったバランス論である。被害者側のプライバシーは少年のプライバシーがどうであるかに関わらず守られるべきであるし、少年のプライバシーも必要以上に侵害されるべきではない。右の誤ったバランス論では、結局、被害者側、少年側どちらのプライバシーも踏みにじられる結果を招くことになるであろう。
ただし、被害者の遺族が、なぜわが子が死んだのか真実を知りたいというのは極めて正当な要求だと思う。このことについては被害者問題のところで後述する。
ひき続く嫌がらせ
私たちの弁護活動が始まったとたん抗議や嫌がらせが殺到したと述べたが、なかにはいつまでも嫌がらせを続けるしつこい中年男性もいた。
この男はどうやら昼間は勤めているらしく、夜になると私の自宅に電話をかけてくるのである。初めのうちは「抗議に行く」などというものだったが、そのうちに「弁護士を外へ出すな」とか、子どもが出ると「お前もあの子(被害者の男児)みたいにしたろか」と言ったり
(後略)