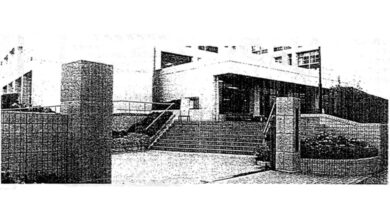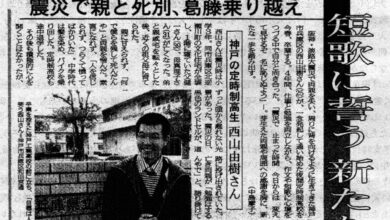定時制高校 青春の短歌

元神戸工業高校教諭 南悟
シングルマザーの歌
昨年夏の大阪市西区のSさんの事件と彼女の境遇を思うにつけ、山口るいさんと定時制高校の値打ちを思い知らされます。
学校と仕事子育て疲れても子どもの笑顔で元気回復 山口るい (2006年)
二◯◯三年三月の神戸工業高校の入学試験の面接室に、「先生ひさしぶり!」と笑顔の山口るいさんが入ってきました。面接官の私も嬉しくて、思わず「元気そうだね」と声をかけました。
阪神大震災の年、一八才で中退した彼女は、小学二年の長男と保育園児の長女を育てる二六才のシングルマザーになっていたのです。
中学を出て私立の女子高に行っていましたが、すぐに辞めて神戸工業高校の友だちの勧めで入学し、中央市場の青果店で働いていました。三才で両親が離婚したため双子の妹とともに父親に引き取られましたが、継母となじめずに一六才で家を出て男性と同棲し結婚しました。学校から足が遠のいていきました。
妊娠七ヶ月の時に阪神大震災があって、大きな揺れにたたき起こされると、お腹の上にタンスが倒れていました。お腹が痛み、救急車を呼んでもつながらず、歩いて病院に行きました。
ロビーには血まみれの人が寝かされていて、壁にもたれたまま息絶える人がいました。
切迫流産の恐れがあって一ヶ月絶対安静で入院しました。震災当時の病院は、水もガスも出ず、食事は缶詰と賞味期限切れのパンだけです。お腹の子どもをどうしても助けたいという思いで耐えました。震災で亡くなる人とひきかえに授かる命だと痛感したようです。
その春、長男を一八時間かけて出産しました。余震があるたびに、「なんとしても育てる」と、赤ん坊の上で四つんばいになり守ったそうです。子育てのために学校を再び辞めました。
長男は、言葉が遅く、仕事で疲れて帰る夫は八つ当たりをし、夫婦間に溝が出来始め、長女が生まれて一年後の一九九八年に、シングルマザーで生きることを決意して離婚しました。子どもを実家に預け、商店街やパチンコ店で働きました。子どもは二人とも、発達障害の一種であるアスペルガー症候群と診断されましたが、彼女はそれも個性として受け止めていたようです。
二◯◯一年、山口さんは交通事故に遭い、後遺症で自律神経失調症の症状がひどくなり、睡眠薬に頼って自宅にひきこもる生活が二年間も続きました。中卒で二人の子どもを抱え、何の資格も無く、将来の自分に悲観して生きる望みを失い、何度も自殺を考えました。踏みとどまれたのは、やはり子ども二人の姿でした。震災で亡くなった命とひきかえの子どもの命なのだと。
そんな頃、子ども二人の手を引いてコンビニからの帰り道、神戸工業高校の生徒募集の張り紙が目にとまりました。思わず、「お母さん、もう一度学校に行くよ」と声にしました。
自律神経失調症の不安定な体調で、かかりつけの主治医の反対もあり夜の学校が続けられるか不安でした。けれども、学校の雰囲気は彼女にとって優しかったようです。二度の高校中退、同棲、震災、出産、子育て、離婚、シングルマザー、と安らぎのない生活であった彼女も、久しぶりの学校、年下の級友、顔なじみの先生、ほっと一息つけたといいます。
授業には、よく子ども連れで登校し、隣の席に座らせて漢字帳や宿題をさせていました。周りの級友もよく手伝い遊んでくれました。毎日、朝五時からの朝食の支度をして、子どもを小学校と保育園に送り出し、勤めが終わった夕方、二人の手を引いて登校しました。続かないと思った学校も、なんとか続けられました。国語の授業で、勉強の「勉」も分娩の「娩」も免許の「免」も、全て女性が出産する姿が感じになっていることを知って、「私はすべて経験している、自分を褒めたくなったよ」と、子育てしながら学び働く誇りを語ってくれました。
同じクラスに一年以上も不登校であった男子生徒の原田君がいました。山口さんは、これまでの生きる望みをなくしていた自分と重なり、励まし続けました。車で駅まで送迎したり、自宅に呼んで子どもと遊ばせご飯をご馳走しました。「私もひきこもり」「みんなお母さんのお腹痛めて生まれてきたんだよ、しっかり生きよう」と声をかけました。ある日、原田君は、「友だちにインターネットで馬鹿にされ秘密ばらされた」と不登校の原因を打ち明けてくれました。「生きていくための辛抱だね」と励まされた原田君は、その一言で学校を続け卒業できました。
山口さんは、現在三二才。交通事故の後遺症が再発して目まいがしてふらつき、仕事ができないので生活保護を受けての生活です。子どもは中学三年と小学校六年になり、ずいぶん手がかからなくなりました。この正月、留守中の自宅マンションが漏電の火事で焼け、連絡が入って駆けつける途中交通事故を起こして車を大破させました。家財道具は全て失いましたが、中でも「へその緒」二つを失ったのが悔しいと言っていました。
辛い出来事ばかりの連続ですが、「しんどいことばかりだけど、人間は生きているだけでも素晴らしい」と言います。
高卒の資格を得て、友だちと計画していた介護福祉士になる夢も果たせそうです。シングルマザーの友だちが看護師になったことも励みです。パソコンを使って、同じ障害を持つ子どもの親とつながりはじめました。
山口さんは、昨春、兵庫県教育委員会が発表した、阪神地域の定時制高校三校の統廃合計画案に反対する文章を書いてくれました。
「定時制高校は、勉強だけではなく、人として大切なものを多く学べる場です。私は、定時制高校がなかったら、せっかく見つけた夢、将来の計画を、全て諦めなければいけないところでした。
先日、私の家が火事になってしまい、母子家庭の我が家は燃えた家財道具の後片付けも経済的な余裕がなく業者に頼めないといった最悪の状態に陥っていました。そんな時、何人か先生達を集めて協力するよ、と先生から連絡がありました。途方に暮れていた私は、先生の言葉が本当に嬉しくて、家族のように思えました。そんな学校が他にあるとも思えません。定時制高校は、私にとっては、なくてはならない場所でした。もちろん、私のように、定時制高校を必要としている人は大勢いると思います。どうか、なくさないで下さい。」
その時の歌です。
定時制 家族の様な 楽しい仲間 卒業しても 今も変わらず (2010年)
 生きていくための短歌 (岩波ジュニア新書 642)
生きていくための短歌 (岩波ジュニア新書 642)
南悟(著) / 岩波書店 / 2009年11月21日
<内容>
昼間働き夜学ぶ、定時制高校の生徒たちが指折り数えて詠いあげた31文字。技巧も飾りもない、ありのままの思いがこめられている。働く充実感と辛さ、生きる喜びと悲しみ、そして自分の無力への嘆き。生き難い環境の中で、それでも生き続けようとする者たちの青春の短歌。
 ニッカボッカの歌: 定時制高校の青春
ニッカボッカの歌: 定時制高校の青春
南悟(著) / 解放出版社 / 2000年5月1日
<内容>
失敗や挫折や障害が癒され、人として生きる力が与えられる定時制高校の生徒たちの短歌、作文を紹介。NHKドキュメンタリー番組で放映。
 定時制高校青春の歌 (岩波ブックレット NO.351)
定時制高校青春の歌 (岩波ブックレット NO.351)
南悟(著) / 岩波書店 / 1994年7月20日
<内容>
「大阪で道路舗装し夕映えの神戸の夜学に車を飛ばす」毎日、汗と油にまみれて働きながら、通学する夜間定時制高校の生徒たち。短歌に詠みこまれた喜び、悲しみ、悔しさ、そして恋─青春いっぱいの姿を教師が綴る。
Sponsored Link