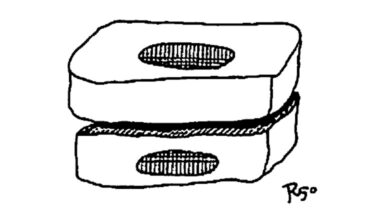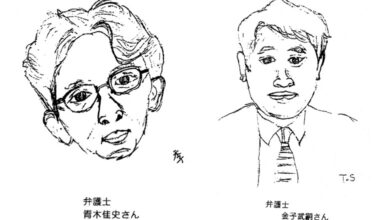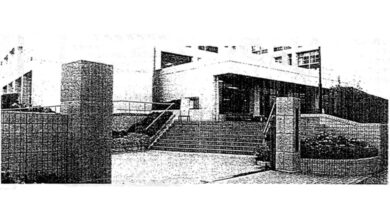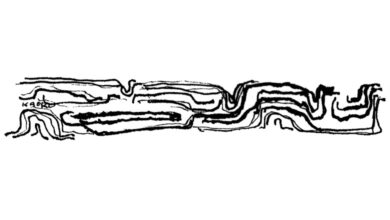校門改修公金支出賠償請求訴訟
二次「判決」に思う

去る10月30日、神戸地裁で門扉の撤去(93年7月30日午前11時50分)につき起こした第二次訴訟に予想通りの光栄なる敗訴判決をたまわりました。
即日、私たちは原告•支援者•弁護士の協議の上、控訴手続きをとり、先に高裁で審理中の第一次訴訟と合体して、ひきつづき追求してゆくことになりました。
これまでの公判の中で公的財産処分の手続きの不備や文書の欠落、あとからつじつまあわせの書類作成等。そのズサン拙速の状況が明らかにされ、また、門扉の撤去そのものが、彼らの責任のがれ•事件かくし•スリ替え•風化策でしかないと誰の目にも明らかであるにもかかわらず、書類不備などは「この程度は問題なし」。そして、門扉撤去も「校長の権限内のこと」だといった判決であった。
何が故の住民訴訟であるか、十分承知しながら、その内容に一歩も踏み込もうとしない、ただただお上み擁護の判決文には毎度のこととは言え、当方としてはあきれて笑うしかない。
何年もかけてこの程度の審理をしかやれない裁判とはいったい何かと、これでは住民訴訟制度そのものが、役所の不正•不法•不当をかえって正当化するための緩衝壁になっていると。これでは裁判(司法)に中立性を期待するのは、お人好しだということにしかならない。
それにしても、こんな空しさを十分承知の上で「原告にかわってでも、この裁判は継続して行きたい」との、これまでの金子主任弁護士他の弁護団の意欲と労苦には頭が下がる。
この一年も数々の教育事件、教師の暴力沙汰は続発し、九州では女生徒が殺されてしまった。無念としか言いようがない。そして、それ故、この裁判もやめるわけにはゆかないのである。
引きつづき、よろしくご支援下さい。
原告 曽我陋
95.11.3.