石田僚子さん追悼20周年記念文集
自分の内を見つめて
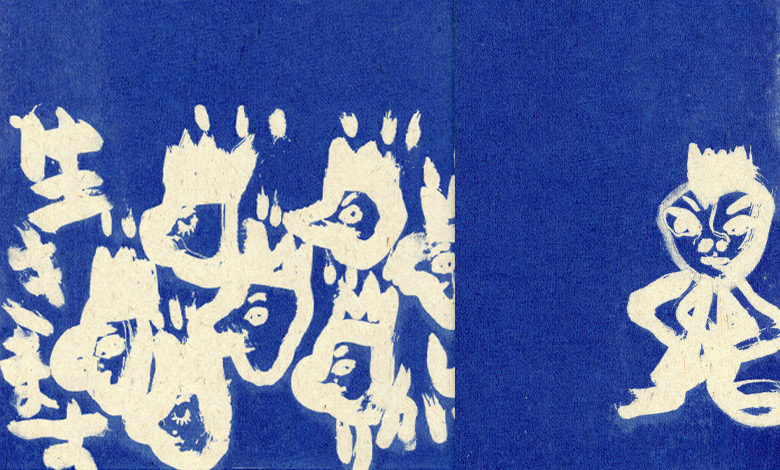
木島 知草
「するべきことは何なのか」と問われつづける時代に命をまんなかにおいてくらしていないと、気づかぬうちによかれと思いこみ加害者になってしまう自分の弱さをいつも感じています。
りょうこさんの命に手を合わせ祈り、誓います。
この「おそれ」を忘れず「してはならないことは何なのか」を問い、自分の内をみつめてくらしていきますね。
(きじま・ちぐさ がらくた座人形劇屋)
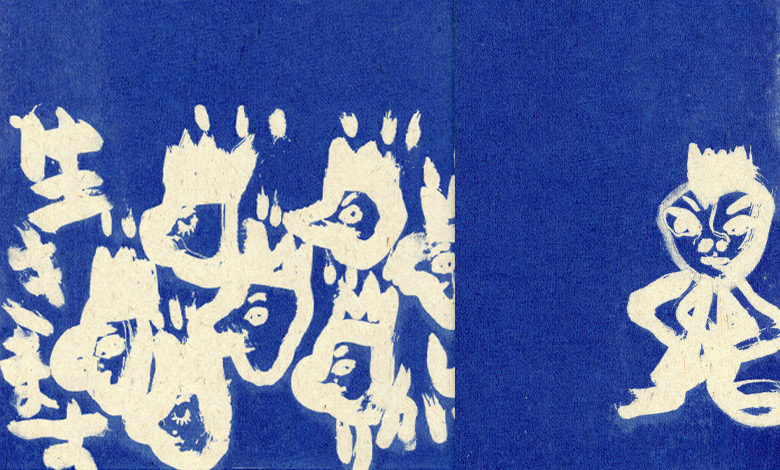
木島 知草
「するべきことは何なのか」と問われつづける時代に命をまんなかにおいてくらしていないと、気づかぬうちによかれと思いこみ加害者になってしまう自分の弱さをいつも感じています。
りょうこさんの命に手を合わせ祈り、誓います。
この「おそれ」を忘れず「してはならないことは何なのか」を問い、自分の内をみつめてくらしていきますね。
(きじま・ちぐさ がらくた座人形劇屋)