門前追悼
石田僚子さん追悼28周年行事のお知らせ
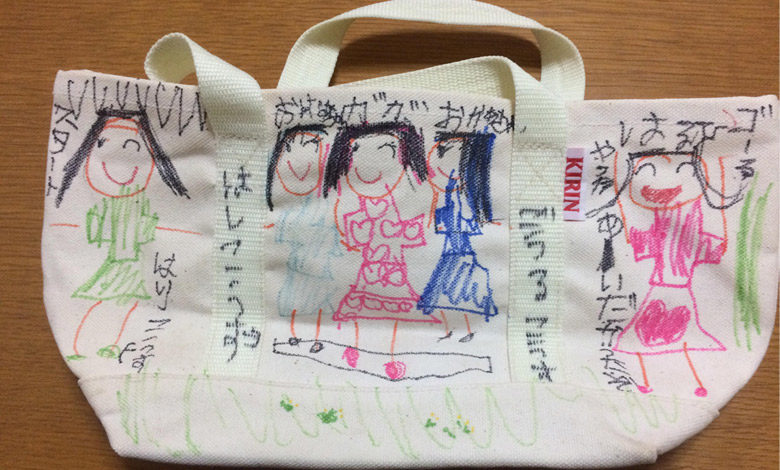
石田僚子さん追悼28周年行事
7月6日(金) am8:30〜9:00 『兵庫県立神戸高塚高校門前追悼』(西神中央駅徒歩10分)
am10:00〜 『中村羅針さんコンサート』
(神戸電鉄押部谷駅徒歩10分 レンガの家 電話番号 078-995-2933)
中村羅針さんへのご寄附のお願い
事件が起こった時から毎年、石田僚子さんのことを路上で話したり唄ったりして、集めたカンパで毎年沢山のカーネーションを献花し続けて下さったことの大きさを今、改めて感じております。東京から車で前日に来られ、カンパで買ったカーネーションを早朝から一人で並べ続けて下さいました。28年目の今年も続けておられます。
下記の口座にご寄附賜りますようお願いいたします。
口座番号:ゆうちょ銀行 01110-4-54084
口座名義:生命の管理はもう止めて






