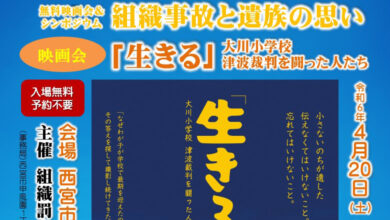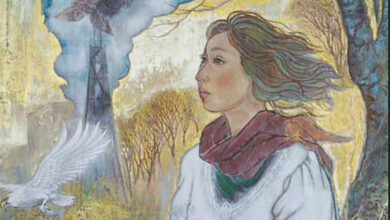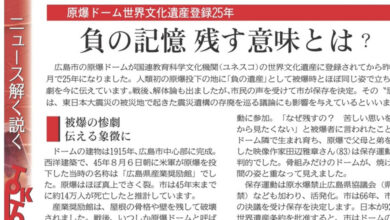秋葉原事件についての勝手なアセスメント
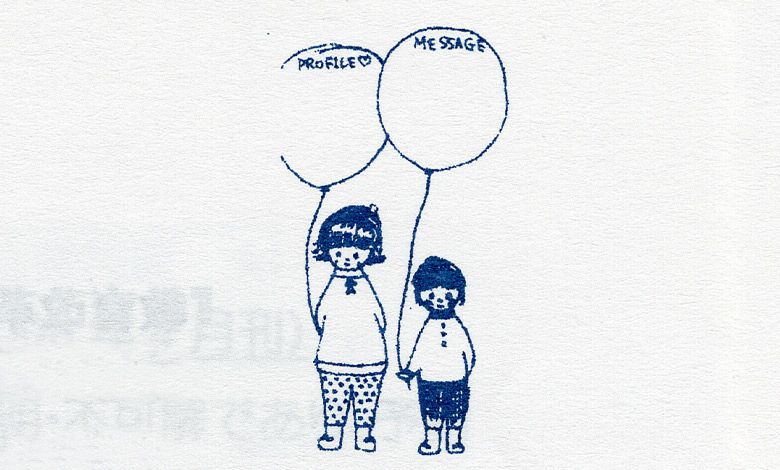
弁護士 峯本耕治
この原稿を書き始めた時には、先頃友人である松本伊智朗さん(札幌学院大学の先生です)が出版した「子どもの貧困」(明石書店)をテーマに書こうと思っていたのですが、今日、秋葉原で信じられないような通り魔事件が起こりましたので、テーマを突如変えて書きたいと思います。
発生日である6月8日は、7年前の大阪教育大学附属池田小学校事件の発生日と同じです。とても偶然の一致とは思えず、犯人は池田小学校事件の情報をネット等で得ていて、わざわざ同一日を狙ったのではないかという気がします。詳しくは書けないのですが、私は、この数年間、池田小学校事件で非常に深刻なPTSD被害を受けた子どものケアに関わってきました。今回のような事件が起こると、池田小事件を体験した子どもたちが事件当時の悲惨さを思い出して不安定になるのではないかと、本当に心配になります。
今回の事件については、今後、犯行に至った背景•原因等が明らかになっていくのだと思いますが、一般的に、子どもや青少年の重大事件の多くには、次の3つの共通要因があると言われています。それは、①親子関係における情緒的な愛着上の障害や課題、②その子ども自身が抱えてしまっている発達上の課題、③きっかけとなる強いストレス要因又は蓄積したストレス要因です。今回の事件についても、犯人の25歳という年齢からして、これらの3要因の存在がわかりやすくみえてくるのではないかと思います。
余りにも無茶苦茶な犯罪ですので、「背景•原因なんか、どうでもエエ」と言いたくなりますが、それでは、何も教訓を導くことができないので、報道されている内容がある程度真実であることを前提として(たいへん脆い前提ですが)、あえて独断的にアセスメントしてみます。
①愛着障害というのは、これまでも何度か書いたことがあるかと思いますが、「子どもが親から無条件に愛されている、大切にされているという実感を持てていない親子関係」のことです。既にマスコミで「小中学校時代は成績優秀だったが、非常に切れやすかった」「お母さんは非常に教育熱心で厳しかった」「無理矢理、勉強させられていた、よい子を演じるのは得意だったと本人が言っていた」「県内有数の公立進学校に進んだが、高校の最初のテストでふるわず、かなり落ち込んでいた」「その後は中以下の成績で、全く目立たなくなった」「友人の大半が大学に進学する中で、自動車整備の短大に進学した」等の情報が報道されています。
愛着障害にも様々な原因があり、身体的な虐待やネグレクト(養育の怠り)等に限らず、極端な過保護•過干渉など、親による行動支配や心理的支配が強すぎる家庭環境、勉強等に関するプレッシャーが強すぎる家庭環境等からも生じることが少なくありません。このような環境の中では、子どもはいつも親の顔色や評価を気にしなければならないため安心できず、また、自発的な動機による努力や成果ではないため結果が出ていても自信につながらず、その結果、本当の意味での「自尊感情•自己有用感」や「人への基本的信頼感」が育ちにくくなるのです。自尊感情や人への基本的信頼感は、対人関係のベースになるものですから、それらが弱いと人間関係の中で様々な問題やしんどさを抱えやすくなります。
今回の事件の犯人についても、上記の報道内容は、プレッシャー型の愛着障害の存在を感じさせる情報です。プライドは高いけど、内心では自信がなく、切れやすかったであろうこと、高校になって成績優秀という居場所を失い、初めて大きな挫折を味わった時の落ち込みや傷つきの激しさ等が容易に想像されます。報道によると、アニメオタクだったということですが、そんな中で、アニメやゲーム、ネット等に居場所を求めていくことになった可能性は高いと思われます。
また、②の発達上の課題とは、いわゆる発達障害の意味ではなく、たとえば「感情のコントロール能力が低く、切れやすい、攻撃的になりやすい」「わがままが我慢できない」「性的な逸脱行動や暴力行為に対する抵抗感の薄れや、認知の歪み」「人の言動等について認知が歪みやすく、極端に被害妄想的になったり、極端に傷ついたり、落ち込みやすい」「自分の気持ちや感情を表現することが苦手で、怒りや、悲しさ、不安、ストレス等を抱え込みやすく、一時にそのストレスを爆発させてしまう」「内心はしんどいにもかかわらず、いつも良い子を演じてしまう」「物事に対して、極端に逃避的•回避的になってしまう」「極端に視野が狭くなったり、しんどい居場所探しを繰り返し、バランスのとれた行動ができず、対人関係をうまく築けない」等の自立していくためのスキルや対人関係スキルにおける課題のことです。愛着障害からくる自尊感情や基本的信頼感の低さを抱えている場合には、このような発達上の課題を抱えやすくなります。
今回の犯人についても、もともと、自尊感情や基本的信頼感が十分に育っていなかった中で、進学高に入学して勉強ができるという居場所まで失ったようです。実は、私も高校入学当初はダメな自分に直面して、部活という居場所を見つけるまで、激しく落ちこみました。おそらく、彼は、その孤独感や不安感を誰にも相談できない中で、居場所を求めて、アニメやゲームというバーチャルな世界にはまっていった可能性が高いと思われます。大学進学にも挫折し、自尊感情が満たされる安定した居場所が見つからない中で、このバーチャルな世界に極端に傾倒していき、それが最終的に、視野を極端に狭め、被害妄想的な感覚やその裏返しとしての誇大な自己愛感情、人を殺すことについての認知の歪み、結果に対するイマジネーション力の喪失等を招いたものと思われます。今回の事件の非現実的な程の無茶苦茶さは、バーチャルな世界からくる認知の歪みを抜きには語れないと思います。昔は、ゲームやネットはなかったので、居場所探しに苦労したのですが、今は、バーチャルな世界に簡単に逃げ込めてしまうのが怖いところです。
最後に、③のきっかけとなる強いストレス要因も重大事件には付き物です。たとえば、中3になって進路への不安が非常に強くなる、信頼していた友人との関係が急激に悪化して孤独感を募らせる、親からの勉強プレッシャーが極端に強まった、信頼していた大切な人を失いどうしようもない寂しさや孤独感に襲われる等の何らかの強いストレス要因が引き金となるのが一般的です。
今回の事件では、事件の直前に、6月で派遣契約を打ち切られると言われたこと、職場で作業服を巡るトラブルで犯人が激高していたこと(自尊心が激しく害される出来事であったことが想像されます)等が報じられていますが、これらは彼にとって本当に大きなストレスとなっていて、事件の最後の引き金になったものと思われます。影響の程度は判りませんが、若者の不安定雇用の問題や将来への希望の抱きにくさという現在の日本社会が抱える課題が関係していることは間違いないと思います。
今回の事件においても、親子関係や友人関係がしんどくなる中で愛着上の障害や課題を抱えた子どもが増えていること、その中で、上記のような発達上の課題を抱え、未成熟な自立できない状態で大人になっていく若者が増えていること、携帯やネットがその傾向に益々拍車をかけ、それだけでなく大きな認知の歪みをもたらす危険な存在となっていること、若者の不安定雇用や格差社会の傾向が強まる中で一般的に若者のストレスが高くなっていること等の背景は指摘できるのではないかと思います。
余りにも異常で、悲惨な事件ですので、どうしても情緒的•感情的な報道が中心になってしまいますが、科学的な視点から背景•原因を導き出し、社会政策的な手当てが必要と思うのですが、なかなかそうはなりません。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。