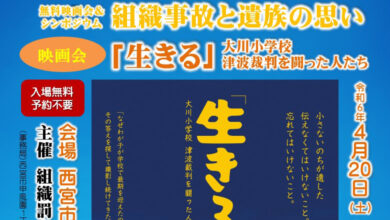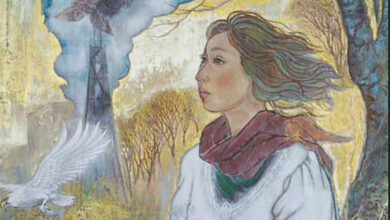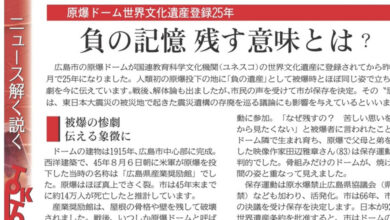日本の風景① 「格差社会」の根源としての派遣労働
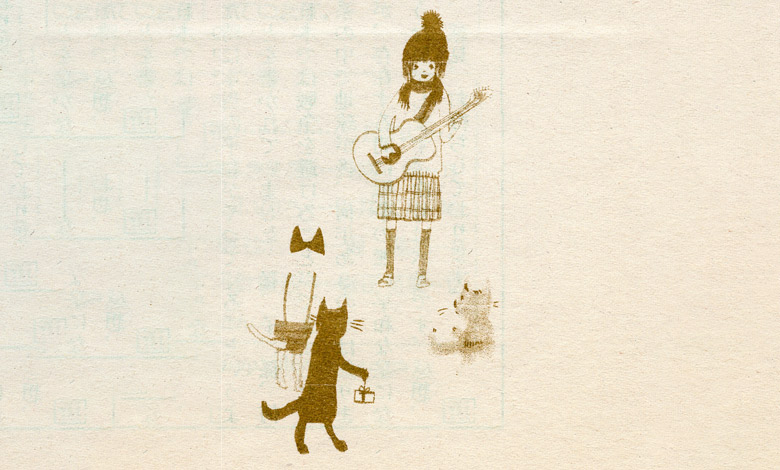
堀蓮慈
労働組合が強いんで有名なオーストラリアから日本に帰って来ると、日本では労働者の権利が守られてない、いうんがようわかる。その典型が派遣や。教育問題いうんは結局のところ労働問題から派生してる(日本の学校教育は、有利な仕事につくことがほとんど唯一の目的で、そこに国家主義の味付けが混じってる)んやから、ちょっと労働の問題に着目したい。現場の教師にとっても無関心ではおれんはずや。
派遣会社いうんは昔で言うたら口入れ屋で、賃金をピンハネするわけやから、本来の労働法制の中ではあってはならんもんで、特殊な専門職のみに認められてたんや。専門職なら、一般の労働者より高給が得られるから、特に問題は生じんかった。ところが小泉「改革」で、今やほとんど全面解禁されてる。その結果、派遣先の企業は自由に人を切れるし、派遣元では労働者の権利を保障してないし、で、資本の好き放題に労働者を搾取できるようになった。法律いうんはえらいもんで、1本の法律で社会をガタガタにすることができるんやな。逆に立て直すんは難しいんやが。
労組がしっかりしてて市民社会が成立してるヨーロッパ(オーストラリアを含む)では、同一労働同一賃金が当たり前で、パートタイムは単に労働時間が短いだけやが、日本では「正」社員とそれ以外の労働者との間に「身分差別」がある。そんな状態を容認してきた労組のだらしなさは糾弾されるべきで、それでは正社員の労働条件も守れへん、いうことに気づかなあかんのや。差別のあるところに団結はあり得ん。
賃金を押さえ込むことで、国民の購買力も下がってデフレになってるんやから、デフレスパイラルを避けるには利益を削って賃金を上げるべきなんやが、そういうことを言う経営者はおらんなあ。経営者に、労働条件を切り下げることで利益を上げるのは恥や、いう意識があったら、ここまで状況が悪化してへんはずやが、アメリカ型の新自由主義とやらに洗脳されて、目先の利益を追うようになってしもたんやろな。
国民の側も、「勤勉が美徳」いう道徳に染まってる。それ自体は悪いわけやないが、そのことと、悪い労働条件に耐えることとはまったく別の問題やのに、分けて考えることができずにサーヴィス残業という名の搾取を許してしまう。学校では労働者の権利についてほとんど教えへんしな。「公民」分野でチョロっと教えても、民主主義同様「タテマエ」としてしか受け取られてへんやろ。
今、政権交代を受けて労働者派遣法の改正案が提案されてるが、いろいろ問題があって与党内でも社民党と国民新党から異論が出てる。メディアは、小沢の4億円よりもこういうことを大きく取り上げるべきなんや。皆さん、この件に注目しててください。