刻のつくる味
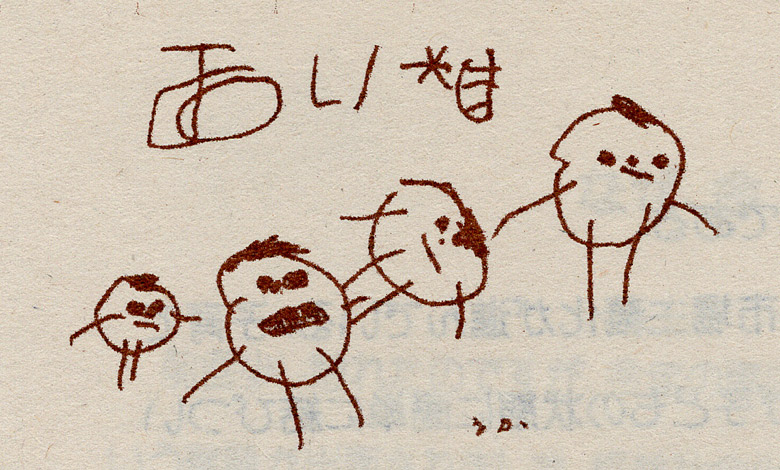
公庄れい
料理にはすべて時間がからむ。時間が味の決め手となるものも勿論多い。この頃のようにスーパーで糠みそ漬けを買う人たちには縁の遠い話だが、明治の中頃に生まれたあるる素封家のおばあさまは、私は糠みそ漬けを食べませんといっていた。
理由は、父親が味にうるさい人で糠みそで漬けたきうりや茄子の色や味のことをうるさく言うので、母親や女中が時間をはかって夜中に起きて漬けたりしていた苦労を、傍らで見ていて嫌だなあと思ったからだという。
わたしの言う刻はそんなうるさいものではなくて、もっともっとおおらかな自然の刻のめぐみのことである。
わたしは沢庵をつけているが、それは三十代から続けていることで、これについてはいささか自信を持っている。ずーと若いとき、夫は何かに腹をたてて家を出ていく夢を見たらしい。その夢の中で出ていく夫を追いかけた私は、沢庵を持たせたのだという。まるで落語の世界のような話であるが、ことほど然様に私の沢庵は自他共に許す味をもっている。
沢庵のように長期間漬けるものは塩、重しと共に時間が重要な要素となる。そのことを田舎暮らしを始めてからいよいよ深く実感させられている。
百姓一年生の夫は作る物の量の加減がわからず大量に大根を作ってしまったことがあった。私は必死でそれを干して漬けた。晩秋に漬けて翌年の春までに食べるのは薄塩に、古漬け用にはよく干して塩も重しも強くする。上がってくる水は布巾に吸わせては絞るということを繰り返し、重しごと樽を大きな布でくるんできつく縛り蝿などが入らないようにして夏を越させる。こうして二夏をすごした秋、漬物樽を開けた私は驚いた。
いい匂い! 沢庵漬けのことを香の物といい、お香こという。その言葉はこの香りを指すのだということが初めて分かった。一夏では出ない香りと味の秘密は酵母の働きなのであろう。二つの夏を越さないとおいしくならない物に麦麹の味噌がある。麦味噌は香りがたかく、甘味が少なくさっぱりしていて野菜ととてもよく合う。この麹に寝かせる小麦は手に入らないので自分で作っているが、早春、青い物の乏しい季節、生え揃った柔らかな緑は鹿を呼び寄せるので彼らから麦をまもるのは一仕事である。が、それらの苦労も味噌樽を開けた時の香りですべて帳消しになる。
梅干しも二夏越すとまったりしてくる。刻と酵母の作ってくれた味に感謝。






