お味噌のことなど
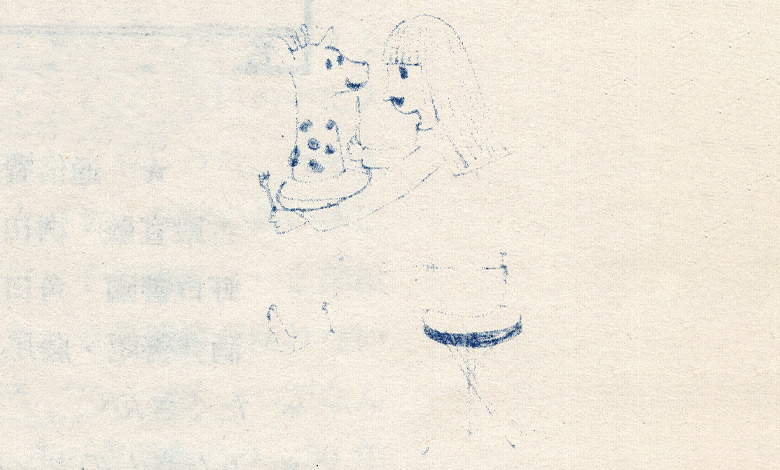
公庄れい
わたしは大体三年に一度味噌をつくる。麦味噌なので麹を寝かすためにまず麦を作る。江戸時代から当地で作り続けられてきた小麦である。緑の少ない冬景色の中で生えそろった柔らかい麦の芽は見るからにおいしそうで、鹿のだいだいだいの好物、油断をしていると草刈り機で刈ったようにきれいにやられてしまう。
どの植物でも稔りの風景は人の心を幸せにしてくれるが、麦秋のあのはずむような景色をこの山村でも目にすることが少なくなった。小麦を作り続けている人に一通りの種を貰って麦をつくり、足こきの脱穀機で脱穀したものを挽き屋さんへ持っていって挽いてもらう。
足踏みの臼だとどんな少量でも挽けるが、挽き屋さんの機械は最低五升からだという。麦を挽くのとお茶を挽くのとは機械が違い、こんな少量の麦を挽く機械はもう製造されておらず、この機械は昭和22年に買ったものだという。昭和28年の豪雨で有田川が氾濫、挽き屋さんは言う。
この機械も何日も水浸しになったけどモーターだけ取り替えてずっと使っとんのじゃで、丈夫なもんや、有田川筋ではうちと、もう一軒この機械を持っとる家がある。この辺りの人らは皆自家用に金山寺味噌を造るやろ、それで小麦をどうしても挽かなならん、ほんま貴重な機械やで。
麦を入れる臼の蓋は木製である。昭和22年、戦後間なしの金属払底の状況が偲ばれる機械である。家ごとに麦をつくり重たく稔った穂は村むらの畑を彩り、汗ばんだ皮膚をちくちくとノギに刺されながら立ち働いたであろう当時の人達の暮らしを伝える機械でもある。そして何百年も続いてきた人々の暮らし方が消え去ろうとしているのを体現している道具でもある。もしこの機械がすり減って使えなくなったら私は大昔から使われてきた足踏みの臼を使おうと思っているし、近所でその臼を備えている無人の家も知っている。が、大多数の人達はもう家で小麦を作ることを止めてしまうだろう。そして小麦の産地からすでに挽いた麦を買うことになるだろう。そしてその産地は外国かも知れない。
何百年もこの風土のなかで作り続けられてきた栽培植物の一つが絶える時かも知れない。だからこそ私はこの小麦を作り続けたいとおもっている。香りの高い麦味噌のおみおつけ、拍子木に切ったきうりに麦味噌をつけて齧る満足感、そんなものを私は捨てたくないのだ。






