学校って何?
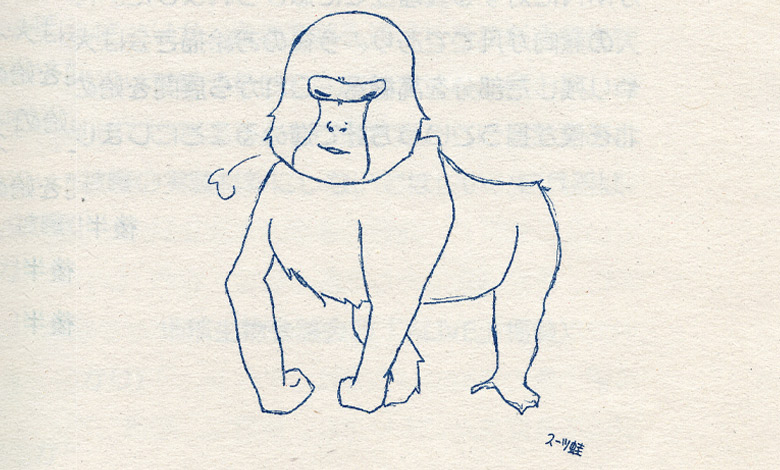
公庄れい
鳥居龍蔵って名をご存知でしょうか。鳥居と同じく小学校中退ながら、日本学士院会員隣文化勲章を遺贈された牧野富太郎の名は多分どなたもご存じの事とおもいます。在野の研究者ながら晩年栄誉に包まれた牧野とは対照的に、ほぼ同時代を生きた鳥居は、昭和14年北京の燕京大学から招聘され、戦後6年間もその大学に勤め帰国後3年にして死去したので、彼の名は知らない人が多いようである。彼の研究の多くは日本のアジアへの進出と軌を一つにし、人類学という分野の性質上勢い軍部の協力支援によらざるを得ず、そうした戦中の研究は戦後のアジア侵略を否とする社会の風潮のなかで埋もれてしまったのであろう。
私は鳥居龍蔵という名前だけは知っていたが、その著書を読んだこともなく経歴なども一切知らなかった。知人の出しているミニコミの紹介で岩波文庫の『ある老学徒の手記』をしり早速読んだのである。そして彼の生一本な生き方と、それに協力する家族のまさに家業とでも言いたいような学問のありかたに驚いたのである。
鳥居は修学の為に22歳で上京、23歳で東京帝国大学人類学教室標本整理係となり、自らの必要とする各教科を聴講して回り知識を深めていく。明治28年、日清講和条約の調印された年、25歳の彼は東京人類学会から派遣されて遼東半島の調査を行う。以後、台湾、蒙古、中国、満州、千島、シベリア、沖縄と国内の調査もふくめて、文字通り席の暖まるときのない生活に終始している。この記録を読むと、東北アジア各地への調査は、それらの地域への進出を図る政府の要請に対して、危険で過酷な条件下での調査に二の足を踏む学者たちが、若くて地位もない鳥居に調査を押し付けたふしがある。
明治3年徳島の裕福な町家に生まれた彼には、男は仕事、妻は内助という考えは無かったらしい。明治34年結婚した妻きみ子は38年に男児を出産、翌年には蒙古喀沁(カラチン)王府女学堂教師に赴任し、翌40年6月には3月に生まれた女児幸子を伴い、夫と三人で蒙古の調査第2回に出掛けている。1年半にわたる調査期間に幸子は支那服と支那靴でよく成長したと鳥居は書いている。このかわいい幼児と若い母親の存在が外国人など見たこともない現地の人達の身体の測定をするという行為をも含めた調査を、どんなに助けたか容易に想像することができる。
このおり北京での軍の関係者の邸へ挨拶に行ったところ「君の今回の蒙古行きに幼女を抱き夫人と同伴せらるるのは、足手まといであり、婦女のこれに加わるは、いわゆる、雌鶏鳴きて暁を報ずで、余の好まざるところである」と大いに非難せられた。しかし私たちは、いかにこの旅行が不可能であるといわれても必ずこれを決行してご覧にいれましょうといって、その邸を去った(23ページ)。
このように鳥居は軍の有力者にたいしてもおもねるところが無かったし、学問上の不正確には目をつむる事ができなかった。大正4年朝鮮の平壌付近の調査をしており、漢式土器を発掘、漢の楽浪郡の跡と推測したが当時の学界の主流はそれを認めず、高句麗の遺跡と主張し、鳥居の研究は朝鮮研究のオーソリティーに対して無礼であると詰責されたのである。彼は「これまで政治家、学者の意見では、漢人は朝鮮に移住せずとなし、その甚だしきに至っては、楽浪、帯方の如きも満州にありとし、従ってかの漢の遼東郡の如きも遼西の地に在りとしていた。これは当時政治上、中国政府に対するポリシーよりかかる意見が一般に行われていたのである。」と書いているが当時の社会情勢が窺われる言葉である。その後、この辺り一帯の古墳が本格的に発掘され、漢墓であることが確認されるが、その発掘メンバーは官学者に限られ彼は除外されていた。
また、鳥居が東京大学助教授の職にあった時、杜撰な調査を資料として書かれた学位論文の審査に際し、これを不可とする彼に対し、主査や他の教授はこの論文を通すようにとせまり、鳥居はこれに納得できず東大に辞表を提出、学部長はじめ教授たちの懇切な慰留にもかかわらず辞意をまげず、大正13年6月大学を辞める。それ以前にもフランス学士院から贈られたパルムアカデミー勲章も贈与証も理学部事務所で紛失しているなど納得できない事があったようである。
鳥居は大学を辞めるとすぐさま自らの家族を所員とした鳥居人類学研究所を設ける。音楽学校出の夫人は、現地で住民の民謡を採譜し夫の研究を補っている。第一次世界対戦の後、ヨーロッパの学問の中心になっていたフランスへ長男龍雄、長女幸子を留学させる。龍雄は残念なことにパリで客死するが、幸子は鳥居のよき協力者になる。次女緑子、次男龍次郎も調査に同行、この調査隊の和やかさがどんなに調査を助けたか想像される。現在アジアの辺境の住民の調査資料は、今後益々その価値を認められるであろう。この手記は昭和8年興安領系の山中の調査記事で終っているが、「人家は一つもない、実に荒涼たる淋しい所で、特に大風大雪でテント内に宿って、これと戦って父子4人は調査したのである。匪賊の危険もある。この行、妻きみ子、緑子、龍次郎が零下30度の寒さとたたかって熱心に尽力してくれたことは感謝するところである」と鳥居は書いている。
小学校2年で退学した彼はこの書の結語でこう述べている。
私は学校卒業証書や肩書で生活しない。私は私自身を作り出したので、私─個人は私のみである。
4月22日の毎日新聞の読者欄の下に「アヤメはショウブではない」という東京本社愛読センター長の一文がある。クロスワードパズルの設問にアヤメとするべきところが、ショウブとなっていたというのである。「菖蒲」という漢字をショウブと読んだ係りが”いずれアヤメかカキツバタ”という譬えを知らなかった故のミスを読者さんから指摘されたというのである。「パズルファンの厳しい目に学びます」と書いているが、厳しい、ではなくて当前の、と言うべきではないのか。多分有名大学を出ているであろう記者諸氏が、この指摘を厳しいとは頷けない感覚である。
だから、最初に戻って学校って何?
 ある老学徒の手記 (岩波文庫)
ある老学徒の手記 (岩波文庫)
鳥居龍蔵(著) / 岩波書店 / 2013年1月17日
<内容>
鳥居龍蔵(1870-1953)は小学校を中退し、独学自修した。考古学•人類学を学ぶために上京。帝国大学理科大学人類学教室標本整理係となって研究を始める。飽くなき探究心で国際的な業績をあげた稀有な民間学者の自伝。
Sponsored Link







