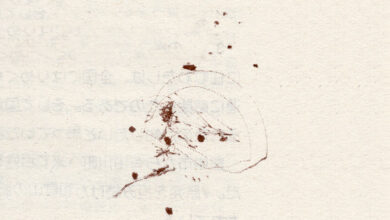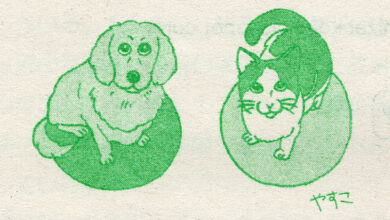いじめは前よりしんどくなっている?!

弁護士 峯本耕治
いじめ問題について書くか、児童虐待防止法の改正について書くか迷っていますが、早く書かないと所さんに叱られますので、決断して、いじめについて書くことにしました。
昨年11月頃から大きな社会問題になった「いじめ自殺」の問題は、ようやく、その連鎖が止まり、落ち着いてきました。しかし、当たり前のことですが、子どもたちの世界におけるいじめ問題の深刻さは、何も変わっていません。
聞くと思い出されるかもしれませんが、過去にも、いじめ自殺の問題が大きな社会問題になりました。いじめは、だいたい10年ごとに大きな社会問題となって、同じことがくり返されてきています。約20年前には「葬式ごっこ」という言葉が有名になった鹿川君事件、約10年前には大河内君事件がありました。いじめ自殺が相次いで起こり、そのたびにマスコミで大々的に取り上げられ、学校•家庭における積極的な取組の必要性が訴えられました。その都度、文部科学省や教育委員会も、いじめ防止の通達やガイドラインを出していて、その内容にも大きな違いはありません。学校から教育委員会へのいじめ問題の報告件数も、大きな問題として取り上げられると、その直後は急増するのですが、数年すると報告件数が激減し、10年位でいじめ自殺が大きな社会問題として取り上げられるというパターンを繰り返してきているのです。ですから、いじめ問題は、当然の事ながら新しい問題ではなく、子どもたちの世界では、長期間にわたって深刻な問題であり続けてきた問題です。
しかし、私自身の率直な印象としては、過去10年間に、いじめは、より深刻さを増してきたように思います。高塚ニュースでもこれまで何度か書いているのですが、それは、子どもたちの人間関係が本当にしんどいものになってきていると感じるからです。
今のいじめの大きな特徴としては、昔以上に、「何がきっかけでいじめの対象になるかわからない」、「誰でもいつでもいじめの対象になる可能性がある」という意識を、多くの子どもたちが持ってしまっている点です。いじめの対象となりやすい子どもの特徴が例として挙げられることがありますが、今は、たとえば、勉強ができるとか、クラスの中でリーダーシップを発揮するなどの、以前であれば、肯定的な評価の対象となる事柄でも、一歩間違えばいじめの対象となってしまいます。また、ちょっとした気まずい出来事や人間関係の軋轢が、すぐに無視や疎外することにつながってしまいます。「嫌い」、「好きじゃない」等の感情が、そのままストレートに、無視することや攻撃的な言動につながりやすくなっています。
そのため、子どもたちは、クラスや友人グループの中で、「自分がどういう言動をするのがより安全なのか」、「どういうポジションを取るのが良いのか」ということを、常に気にしなければならなくなっています。友達にどう思われているのかを過度に気にしなければならない状況が生まれているのです。
私自身も子どもたちのこのような雰囲気を実感することがありました。私が学校評議員をしている高校で、生徒会の執行部をしている8名位の生徒と話をする機会がありました。その会話の中で、友人関係に関する話題が出たのですが、参加していた全員から、「友達から、自分が、どう思われているかが大変気になる」という意見が出ました。その内の1人が例として挙げてくれたのが、「授業中に先生から当てられて答える時にも、自分の答えが、先生にどう評価されるかよりも、友達からどう思われるかが気になって仕方がない」という話です。「ほかの皆はどう?」と尋ねると、やはり、全員が「すごく気になる」という返答でした。簡単に言えば、あまり見事な答えをすると「ええかっこしやがって」と思われたり、反対にあまり不細工な答えをすると「アホか」と思われてしまい、それがいじめや浮きにつながってしまうかも知れない、こんな感じの不安です。「いつ頃から、そんな風に友達の目が気になり出した」と聞くと、大体が「小学校の高学年頃から」との回答でした。思春期前頃から、子どもは他者の評価をかなり気にし始めるものですが(それも重要な発達段階と言って良いと思いますが)、それが余りにも極端になってきているのです。
もう一つ同じような経験がありました。私の知人も全く同じ経験をしたのですが、大学の講師をしていた時に、講義中に学生の意見を求めても、余りにも手が挙がらないので、講義後にある学生に理由を尋ねたところ、びっくりする返答が返ってきました。「自殺行為だから」という答えです。わざわざ目立つことをして、いじめられたり、浮いたりしたくないという意味です。
こんな関係は、余りにも、しんどすぎます。自分を素直に表現できない萎縮的な友人関係の中では、対人関係スキルの学びも貧困なものになってしまいます。もちろん、いじめも簡単に起こります。これほど過敏にならないといけないということは、実際に、ちょっとしたいじめは、日常の風景として存在しているということを意味しています。
そして、何よりも、こういう関係や雰囲気の中ではブレーキがかかりにくく、簡単にエスカレートする危険性があります。たとえ、いじめが良くないことだと判っていても、自分が被害を受けることを避けるために、より安全なポジションを選択することになってしまうからです。いじめに気づいても、止めろとは言わない方が安全ですし、また、周りの状況によっては自分の身を守るために、いじめに参加することが安全な選択ということになってしまうからです。
大人社会を見ていれば明らかなように、いつの時代にも、どんな人間関係においても、いじめや、いじめ的な言動は存在しますが、いじめのエスカレートを防止できるかは、集団が持っている力、クラス全体が持っている力や雰囲気が大きな意味を持ちます。紹介したような子どもたちの人間関係•雰囲気の中では、抑制力は全く働きません。私は、これが今のいじめ問題の最も深刻な特徴ではないかと思っています。
子どもたちの人間関係が、ここまで来てしまったときに、どうしたらよいかを考えると絶望的な思いになりますが、やはり、親、教師が、子どもたちに、そのような人間関係の問題点を率直に伝えながら、連帯感に支えられた(表面的な仲の良さではない)人間関係作り•クラス集団作りを積極的にサポートしていく取組が必要だと思います。
私の印象ですが、今の子どもたちは、親や教師から、そのような人間関係作りに関するダイレクトなメッセージや情報提供をほとんど受けず、学びもなく、自分たちも問題点に気づかないまま、しんどい人間関係を形成してしまっているように感じます。ですから、大人が、自分たちが正義だと感じる価値観を率直にぶつけ、導いていけば、子どもたちは、想像以上に大きな吸収力を持っているように思います。もちろん、早ければ早いほど、影響力は大きいので、小学校時代からの早期の取組が必要です。
今のいじめについて、もう少し書きたいことがあるのですが、おそらく字数の限界を超えつつあるように思いますので、ごく簡単に気になる点を挙げたいと思います。
一つは、携帯電話とメールが大きな役割を果たしていることです。人間関係の難しさの原因にもなっていますし、いじめの陰湿化や攻撃性の強まりにも大きな役割を果たしています。メールやネット利用に関する教育、メディアリテラシー教育が本当に重要になっています。
それから、もう一つ、いじめに関する調査から、多くの子ども(約8割)が、「学校の先生がいじめに気づいていた」と感じていることが明らかになっています。これは深刻な結果です。つまり、「先生は知っていたけど、きちんと対応してくれなかった、守ってくれなかった」という感覚を持っている子どもが多数を占めていることを意味しているわけです。こういう状況の中では、子どもたちはいじめの被害を受けていても、それをなかなか話してくれません。先生が守ってくれるとは思えないからです。また、それだけでなく、教師に対する信頼感を大きく下げる要因となっていて、いじめへの対応だけでなく、教師の教育活動や指導全般を困難なものにします。成功するかどうかは別にしても、いじめ問題への積極的な取組は、子どもと教師の信頼関係の維持•回復にとっても重要なポイントになります。
最後に、これは現代のいじめに限りませんが、子どもはいじめを受けていても、それをなかなか訴えてくれません。親も教師も、その理由を知っておく必要があります。いじめが子どもたちの日常的な人間関係の中の出来事であるため、「そこから抜け出すことができない」「親や教師に言ってもどうしようもない」「誰も助けてくれない」という無力感を持ちやすいこと。「親に心配をかけたくない」という思い等々。様々な理由がありますが、最大の理由は、いじめが自尊心に関わる問題であるという点です。自分がいじめを受けているということを認め、人に助けを求めること自体が、「いじめられる=社会的価値の乏しい存在である」、「自分が悪いからいじめられる」と認めることにつながり、そこから、子どもたちは、「自分がされていることをいじめと思わない」「うすうす感じていても思いたくない」「思っても言えない、言いたくない」という気持ちが生まれてくるのです。
子どもたちのこういう思いを踏まえて、いじめ問題には取り組んでいく必要があります。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。
Sponsored Link