発達障害と発達障害的な症状について
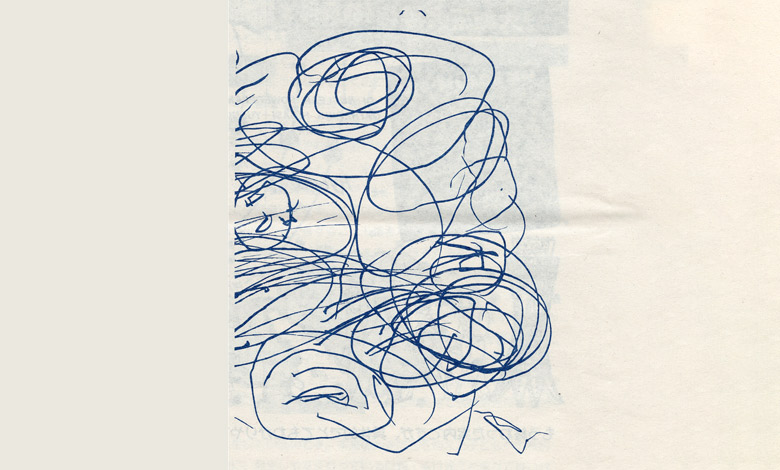
弁護士 峯本耕治
御記憶に新しいと思いますが、大阪市議会の維新の会が提案した家庭教育支援条例が、発達障害を抱えた子どもの親の会などの激しい抵抗により撤回されました。
条例中に、子どもの発達障害の原因が親の養育の不適切さにあるかのような条文が存在したことで、親の会から激しい抵抗を受けることになったのです。発達障害は先天的脳機能障害に基づくものと考えられていますから、それが親の養育に原因があるとしたのでは、当然、激しい非難や抵抗を受けることになります。余りにも軽率で撤回に追い込まれることも、やむを得なかったと思います。
しかし、この問題は、実際に学校現場で生じている問題をみたとき、難しい問題をはらんでいます。高塚ニュースでも何度か紹介したことがありますが、近年、学校では、授業中に集中力を維持できず、すぐに立ち歩いたり、友達にちょっかいをだすなどの落ち着きのなさや、教師からの指導に対してすぐに切れて暴力が出たり、パニックになったりするなどの問題行動を抱えた子どもが増えていると言われています。このような問題を抱えた子どもたちは、医療機関に連れて行かれると、ADHDや広汎性発達障害(この名称は今後医学的には使われなくなります)等の診断を受けることが珍しくありません。しかし、実際には、その大部分は、本来の発達障害ではなく、子どもを取り巻く環境(家庭環境、学校環境の双方を含みます)から生じた発達障害的な症状にすぎません。最も基本的なメカニズムとして、家庭におけるネグレクトや身体的虐待、極端な過プレッシャーなどの被虐待の環境に置かれた子どもは、自尊感情や人への基本的信頼感が低くなりがちで、寂しさや不安の裏返しとして、愛情要求や居場所探しが激しくなります。それが、学校という集団教育の中に入ると、「見て見て行動」としての落ち着きの無さや、激しい自己アピールとして表現されるようになります。そうなると、どうしても、学校では、先生から、注意•指導を受けたり、怒られたりすることが多くなり、結果として、子どもは自尊感情や信頼感を一層低下させ、教師に不信感を持ち、勉強面でもドロップアウトしやすくなり、学年があがるにつれて教師からの指導に対しては、反発や攻撃性を示すようになっていくのです。愛着障害から生じる自尊感情や信頼感の低下、寂しさや見捨てられ感、不安の強さ、その過程で増大していく発達課題(対人関係スキルの低さや悪いスキルの学び)が、問題行動•症状として表現されるのです。このような愛着障害から生じる発達障害的な症状に対して必要なことは、特別な医学的な治療や特殊な教育ではありません。当たり前のことですが、子どもの問題行動が持つ意味の正確な理解(アセスメント)と、愛情保障(愛情•安心感、自尊感情や信頼感を高める取り組み、不安を取り除く働きかけ)と発達保障(しっかりとしたしつけ、対人関係スキルを高める指導•働きかけ)です。また、学校だけでは簡単にできることではありませんが、家庭への積極的な支援や指導により、家庭の愛情•安心•安全環境を少しでも改善することも重要なことです。
このような愛着障害から生じる発達障害的な症状を抱えた子どもを、本来の発達障害であると見立ててしまうと、様々な問題が生じてしまいます。たとえば、学校が、①子どもの問題行動は障害や病気が原因だから学校では対応できず、専門家による治療やカウンセリングが必要だというメッセージを安易に子どもに送ってしまった結果、子どもは見捨てられ感を深め、より一層荒れてしまう、②障害だからクラスの中での指導は不可能であるとして、個別指導に終始してしまい、逆に対人関係スキルを育てることができにくくなる、③障害だと思って、対応に不安を感じたり、構えた対応をしてしまうことにより、子どもにしっかりと向き合って、叱ったり、厳しい指導ができなくなってしまい、結局、愛情保障も発達保障もできなくなる、④愛着障害の根本的な原因となっている家庭への支援や指導の視点を全く持てず、逆に、親と一緒になって、子どもの見捨てられ感を深める対応をしてしまう等の問題です。
実は、このような問題が、近年、学校では頻繁に生じているのです。本来の発達障害を抱えた子どもへの特別支援教育の体制が整備されつつあるからこそ、逆に、発生しやすくなっている問題•掛け違えと言って良いかもしれません。
だからこそ、この機会に、被虐待環境•愛着障害環境から生じた発達障害的な症状を抱えた子どもへの対応については、学校による教育•指導のあり方、家庭支援のあり方を、しっかりと考えるべき時期にあると思います。
 「発達障害」と間違われる子どもたち
「発達障害」と間違われる子どもたち
成田奈緒子(著) / 青春出版社 / 2023年3月2日
<内容>
近年、発達障害と呼ばれる子どもが劇的に増えています。文科省が出している数字を見ると発達障害が疑われる子は、この13年で約10倍に。ただ、35年にわたって子どもの脳•育ちに向き合ってきた著者は、増えているのは発達障害の子ではなく「発達障害もどき」ではないかと話します。発達障害もどきとは一体何か、発達障害もどきから抜け出すにはどうすればいいのか―。臨床経験35年以上の小児科医が、増え続ける発達障害児の中にいる「発達障害もどき」について初めてまとめた一冊です。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。







