一枚の婚礼衣装
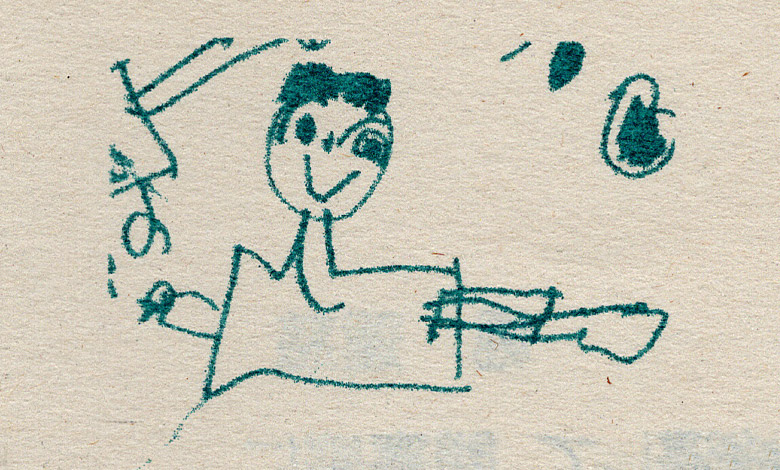
公庄れい
西宮の”くらしのきもの資料館”では現在、「明治•大正•昭和初期の婚礼衣装展」を開いている。昭和6年に結婚した私の母親の物も展示したが、豪華な衣装の中で母の着物は素朴でつつましくいかにも山奥の村の貧乏な親がやっと買い整えたという風情をまとっている。当時庶民の婚礼衣装は黒の留め袖で前見頃の膝から裾にかけて伝統的なおめでたい文様、松竹梅や鳳凰を付けたものが殆どである。総柄の振袖を着た花嫁はよほどのご大身か着物にうるさい母親を持っているかであったと思われる。
私の母のつつましい着物が花園村での花嫁衣装を着た二人目であったと聞いてびっくり。それまでの村での婚礼は縞のお召の着物に頭は桃割れで夜嫁入りしたそうである。頭は勿論自分の髪で、母の場合は高野山まで前日結いにいき、当日の着付けは昔大阪で芸者をしていたという近所の小母さんにして貰ったのだという。そしてその着物もその小母さんに大阪で買ってきて貰ったのだという。
さてその着物であるが文様に使われている色すべて淡いベージュがかったグレイの底から浮かび上がって来ているような色使いで幾輪もの薔薇の花やつぼみがまず目に入る。そして申し訳程度に松と菊が添えられ、なんとも優しい目をした鳳凰が飛んでいるのであるが、その羽は孔雀のようで明かに当時ヨーロッパから入ってきたアールヌーボーの流れを汲んだものである。高野山の奥の寒村のたたずまいとこの最新流行の着物の有り様が面白くて私は芸者をしていたというその小母さんに興味がわいた。
その人は大和下市の人で、母親の連れ子として育ち七つの歳に義父に芸者に売られ十六で二十二も歳の違う小金持ちに落籍されて正妻として村に来たのだという。明治三十年頃に生まれたその人を覚えている人は村にも多いので聞いてみると、賢い人、優しい人、几帳面な人、激しい人、きれいずきな人、料理上手な人、厳しい人さまざまにその印象を語るが、みんな口を揃えるのはその美しさと姿の良さだった。「今テレビで女優さんをようけ見るけどあんな美しい人はおらんなあ」
在所の人々を魅了した人の二十六歳の写真が残っている。高々と結い上げたひさし髪に黒留め袖、一面の波にヨットがそこ此処に浮かんでいる。波もヨットも抽象化されさらっと乾いた文様である。扇子を膝にして椅子に座って何処かを見つめている目は少し悲しげで可憐な少女のような趣がある。
村の娘たちに舞を教えている時に彼女は言ったという。「あんたら私がきついと思うかもしらんけど、私は七つの時に親に売られて舞を仕込まれたんやで、間違うたら金槌で手でも足でも叩かれて、ご飯を食べたり、歩くのにも不自由したこともあった、上手になるよりしょうがなかったんやで、どこにも逃げていく所がなかったんやもん」
彼女、上田正枝さんの選んだ花嫁衣装を私は未来に伝えていきたいと思っている。






