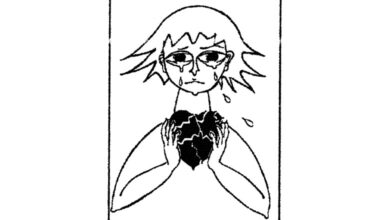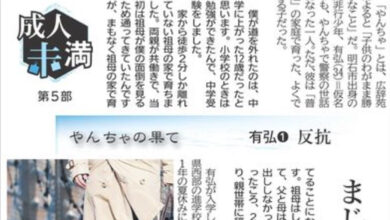イギリスの少年裁判と日本の少年裁判 子どもにとって、どちらが得か?
このように書きますと、イギリスの少年裁判は、子どもに厳しい、冷たい印象になってしまいます。確かに、そういう側面があることは事実なのですが、イギリスの少年裁判を見ていると、それだけでない何か、「子どもの権利を保障する」ということの意味を考えさせる何かがあります。
うまく表現できないので、少年裁判の様子を簡単に紹介したいと思います。
住居の近くに少年裁判所がありましたので、裁判所の許可をもらって、何度か傍聴に出かけました。一日に何件も裁判がありますので、長時間見ていると、色々な場面に出会います。
5件の万引(窃盗)を理由に裁判にかけられた12歳の少年の話です。12歳はイギリスでは中学1年生の年齢です。
少年は、裁判官から5件の万引の事実を認めるかどうかを確認されて、「有罪であることは認めますが、2番目の万引の品物の一部は友達が盗んだものです」と答えました。全く物おじすることなく、堂々としたものです。
犯罪事実の一部の否認なのですが、もともと万引という軽い事件ですので、どちらにしても、処分には影響しません。そのため、検察官、弁護人、裁判官の間で、「少年が認めれば、すぐに裁判を終わらせることができる。その方が少年にとって良いのではないか」とか、「一部でも裁判を取り下げるためには、検察内部の手続が必要になる」などとのやりとりが行われましたが、最終的に、検察官が一部の取下をを検討するために裁判を延期することになりました。
この時も裁判官の少年に対する説明が、何とも素敵なものでした。
「今、もめていたのは、あなたの責任ではありません。私たちは、あなたに、やっていない犯罪をやったと言って欲しくないので、検察官がどうするかを決定するために、正義(ジャスティス)のために、一回、裁判を延期します」
この説明を聞いて、少年が、当然といわんばかりに、大きくうなずいていたのが、大変印象的でした。
この裁判に限らず、裁判官が少年達に語りかける言葉は、大人に対する言葉と同様に丁寧なものでした。多分に英語という言葉の性格が関係しているかも知れませんが。
少年たちの受け答えもはっきりとしていて、言いたいことを堂々と口にします。裁判官も注意すべきごとは厳しく指摘しますが、少年の言い分に対しては、特に感情を害したりすることなく、当然のようにサラッと受け止めています。