アフガニスタン難民とこの国のかたち
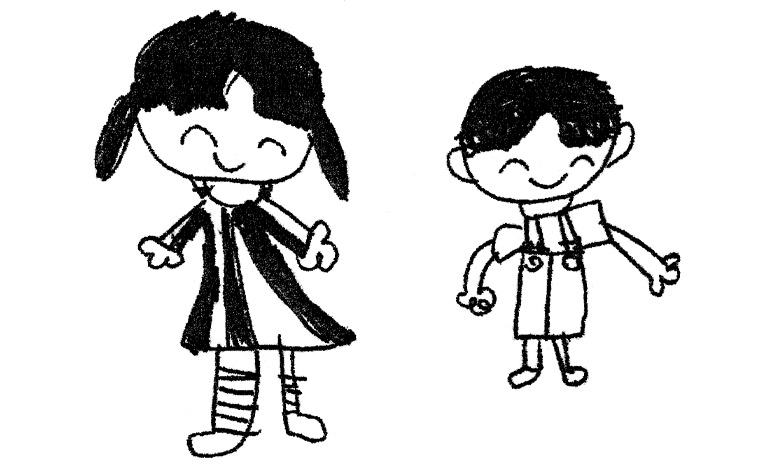
弁護士 秋田真志
今、日本人に「『いのちが奪われる』と聞いて何を連想する?」と問えば、どんな答えが返ってくるであろうか?
事故、病気、殺人、自殺、震災•••。いろいろな答えがあるだろう。しかし、「戦争」という言葉は、あまり出てこないのではないだろうか。昭和が終わり、20世紀も終わり、日本にとって、戦争ははるか昔の過去のことになってしまった。
Iさんから久しぶりの電話をもらったのは、今から1年半前の1999年年末のこと。Iさんは、10年前、弁護士になりたての私がはじめて担当した過労死事件の支援をしてくれ、労災認定獲得に力強い味方となってくれた人物。屈託なく、心優しい熱血漢である。ところが、今度の電話は、なにやら歯切れが悪い。
「秋田さん、忙しいやろな。こんなこと頼んでええかどうか、ほんま迷ってるんやけど•••。」
「なんや水臭い言い方ですね。どないしはりましたん?」
「あの•••大阪にアフガニスタンのハザラ人で難民の人がいるんやけど•••。ちょっと力を貸してくれへんやろか?」
「•••(アフガニスタン?ハザラ?難民?)」
私が、Iさんの紹介で、アフガニスタン人のフセインさんと初めて顔を合わせたのは、2000年問題で日本国中が大騒ぎした年明け早々であった。フセインさんは、49歳という年齢の割には、老けているように見えた。東洋系の面立ちで、仮に日本人だと言われても、それほど違和感はない。しかし、日本語は全くダメ。せいぜいコンニチワ、オハヨウゴザイマス。日本語どころか、祖国がずっと内戦状態だったため、まともな教育を受けたことはなく、母国語のダリ語の読み書きすらできないという。コミュニケーションは、日本語を何とか話せる別のアフガニスタン人の通訳を通じるしかない。それも、シーア、スンニ、パシュトウーン、タリバン、ヘズビワハダット、マザリシャリフなど、はじめて聞く言葉ばかり。知らない言葉が出るたびに意味を確認せざるを得ず、話は一向に前に進まない。Iさんが、頼みにくそうにしていた理由が、十分に理解できた。
しかし、苦労して聴き取った内容は、たどたどしい通訳の日本語とは裏腹に、衝撃的なものだった。内戦が続くアフガニスタンで、パシュトーン人中心のイスラム原理主義タリバンが台頭したのは、1994年。タリバンと対立するヘズビワハダット(イスラム統一党)の中心である少数派シーア派のハザラ人は、もっとも迫害を受けやすい立場となった。現にハザラ人でイスラム統一党の支援者の一人であったフセインさんは、1996年にアフガニスタンの首都カブールがタリバンの攻撃によって陥落した際、タリバン兵士に銃剣で刺し殺されそうになり、命からがら逃げ出したという経験をしている。
九死に一生を得て、家族とともに北部の都市マザリシャリフに逃れたフセインさんに、心の休まる暇はなかった。2年後の1998年、北上したタリバンは、マザリシャリフに侵攻したのである。日本で中古車部品の買い付けの仕事をしていたフセインさんは、ちょうどそのとき、日本にいて難を逃れたが、それ以来マザリシャリフにいた家族らと音信が途絶えてしまった。アフガニスタンに戻れなくなったフセインさんは、アフガニスタンの隣国パキスタンやUAEに行き、アフガニスタンから逃れてくる難民からの情報の中に家族の消息を探し求めたが、伝わってきたのは、悲劇的な内容ばかりであった。マザリシャリフでは、陥落後、タリバンによる大虐殺が行われていたのである。数千人のハザラ人が犠牲になったという。その中にフセインさんの息子や弟も含まれていたことがわかった。妻や幼い娘の消息は沓として知れない。フセインさんは失意のまま祖国に戻ることもできず、1999年7月、来日した。
パキスタンにいる友人から、フセインさんに電話が入ったのは、日本からパキスタンへ戻ろうとしていた9月末のことであった。なんとパキスタンにやってきたタリバンのメンバーがフセインさんを捜しているというのである。マザリシャリフ陥落の際、フセインさんの自宅を捜索したタリバンは、フセインさんをイスラム統一党の支援者と知り、殺害司令書を発行したという。友人らは、フセインさんに、絶対にパキスタンに戻ってくるなと警告した。驚いたフセインさんは、日本入管に難民認定を申請したのである。
難民であることを訴えるフセインさんの前に立ちはだかったのは、日本の難民認定法に定められた「60日ルール」であった。60日ルールとは、難民認定を申請する者は、原則として、日本入国後60日以内にその申請をしなければならないとするものである。難民条約を批准した国の中で、このような期間限定をしている国は他にもある。しかし、それらの国でも、その期間限定を杓子定規に運用する国などほとんどない。期間を守ったかどうかではなく、本当に難民と言えるかどうかが重視されているのである。
当たり前だろう。難民かどうかは、「いのち」の問題である。期間を守ったかどうかという形式的なことが優先されるべきはずがない。しかも60日などという短期間の限定をしている国は、日本を含めごく少数しかない。
ところがである。日本の入管は、日本入国後90日足らずの間に難民認定申請したフセインさんを、60日ルールだけを理由に不認定としたのである。
話はそれだけでとどまらない。フセインさんの難民調査を担当したある難民調査官は、「なんで難民申請なんかするんだ。おれなら家族のために祖国に帰って戦う」と言い放った。そして不認定処分後、ビザの更新を拒否した入管は、一日も早く出国しろとフセインさんに迫り続けたのである。私が、フセインさんと面談したのは、そんな出国命令が繰り返されている矢先であった。その直後フセインさんは、オーバーステイで入管に収容され、強制退去命令を受けることになったのである。その命令書(強制退去令書)には、強制送還先として、臆面もなく「アフガニスタン共和国」と記載されていた。もちろん、タリバン支配下のアフガニスタンである。たとえれば、ナチ支配下のドイツにユダヤ人を強制送還する命令書である。
この強制退去の適法性を争う口頭審理に出席した私は、そこでさらに衝撃的な場面に出くわす。審理官が、アフガニスタンで彼が受けた迫害の数々を詳細に聞き出し、記録し始めたのである。内心私は期待した。「もしかしたら入管は、フセインさんが、難民であることを認めるつもりではないか?」。実際、そのころから、日本でも、それまであまり知られていなかったタリバンの非人道的な行為が報じられるようになっていた。タリバンは、既に国際問題に発展していたのである。日本政府が、それまでの態度を変えたとしてもおかしくはない•••。しかし、私の淡い期待は、審査官の次の質問で、ものの見事にうち砕かれた。
「そんな迫害を受けていたのなら、どうして他の国で難民申請しなかったんだ?どうして日本入国後すぐに申請しなかったのだ?」
その審査官は、60日ルール違反の「自白」を取ろうとしていただけだったのである。
悲しいかな、これが日本という国の一つのかたちである。
今、フセインさんの「いのち」をかけた裁判(難民不認定処分、強制退去令書発付処分取消訴訟)が、大阪地裁で進められている。
 赤ちゃんの虐待えん罪: SBS(揺さぶられっ子症候群)とAHT(虐待による頭部外傷)を検証する!
赤ちゃんの虐待えん罪: SBS(揺さぶられっ子症候群)とAHT(虐待による頭部外傷)を検証する!
秋田真志(著,編集), 古川原明子(著,編集), 笹倉香奈(著,編集) / 現代人文社 / 2023年4月18日
<内容>
日本で虐待疑惑があるとSBS/AHT仮説に基づいて親子分離や捜査が進められるが、海外ではその仮説には問題があるとされ、多くの人が冤罪被害に遭っている。SBS/AHT仮説に基づく虐待疑惑には慎重に対応すべきであり、根本的に見直す必要がある。本書では、この問題を明らかにし、誤った親子分離や訴追を防ぐための対策を考える。
 取調べ可視化―密室への挑戦: イギリスの取調べ録音•録画に学ぶ
取調べ可視化―密室への挑戦: イギリスの取調べ録音•録画に学ぶ
小坂井久(編集), 秋田真志(編集) / 成文堂 / 2004年1月1日
<内容>
適正な手続を実現し被疑者•被告人の防御権を保障する試金石である「被疑者取調べの可視化」について解説。すでにイギリス刑事司法手続に定着している「被疑者取調べのテープ録音手続」に関する調査取材の成果を報告する。
 実践! 刑事証人尋問技術part2: 事例から学ぶ尋問のダイヤモンドルール(GENJIN刑事弁護シリーズ20)
実践! 刑事証人尋問技術part2: 事例から学ぶ尋問のダイヤモンドルール(GENJIN刑事弁護シリーズ20)
ダイヤモンドルール研究会ワーキンググループ(著,編集) / 現代人文社 / 2017年9月20日
<内容>
季刊刑事弁護の大好評連載を書籍化。「成果をあげた尋問」を分析して、「誰にでも伝承可能なルール=ダイヤモンドルール」を体系化すべく研究を行ってきた成果の第2弾。2009年に刊行した前著『実践!刑事証人尋問技術――事例から学ぶ尋問のダイヤモンドルール』での議論をさらに深化し、また、前著では十分に触れられなかった「尋問の組立て方」やそのための「ブレーン•ストーミング法」、「専門家証人に対する尋問」などについても、ダイヤモンドルールを抽出した。
 実践! 刑事証人尋問技術―事例から学ぶ尋問のダイヤモンドルール(DVD付) (GENJIN刑事弁護シリーズ(11))
実践! 刑事証人尋問技術―事例から学ぶ尋問のダイヤモンドルール(DVD付) (GENJIN刑事弁護シリーズ(11))
ダイヤモンドルール研究会ワーキンググループ(著) / 現代人文社 / 2009年4月20日
<内容>
刑事尋問で成功するための「ダイヤモンドルール」を抽出して、解説する。付録DVDでは、ダイヤモンドルールを用いない場合と用いた場合をそれぞれ実演。本とDVDで学んで、あなたも尋問の達人に。










