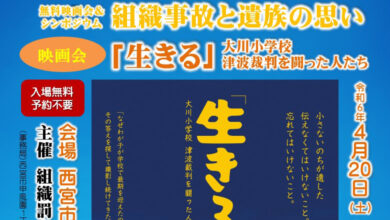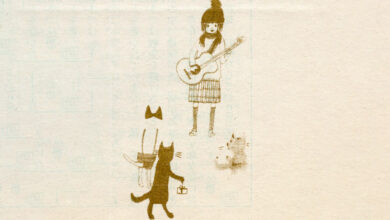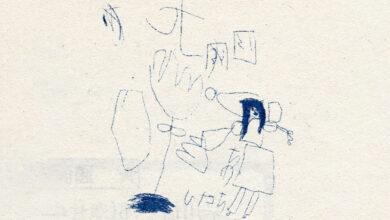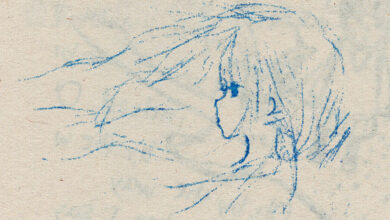ゲーム、携帯電話、ネットは怖い?

弁護士 峯本耕治
今、柳田邦男氏の「壊れる日本人―ケータイ•ネット依存症への告別」(新潮社)という本を読み始めています。ゲームや携帯電話、インターネットが人間の心や子どもの発達に影響を及ぼす危険性に警鐘を鳴らす内容で、特に、発達段階にある子どもに及ぼす影響の大きさをストレートに訴えています。
私も、最近、ゲーム、携帯電話やインターネットが持つ危険性を感じることが少なくありません。子どもにかかわる問題の背景に、子どもたちの対人関係能力•コミュニケーション能力の低下の問題があります。切れやすかったり、パニックに陥りやすい子ども、自分の気持ちを素直に表現できない子ども、人を傷つけやすい子ども等が増えているといわれています。今の子どもたちのしんどい面として挙げられているこれらの特徴は、どれも、子どもたちの対人関係能力•コミュニケーション能力の低下を示しているものです。
対人関係能力は、当たり前ですが、様々な人間関係や体験を積むことにより身に付いていきます。その中心となるのが、親子関係と共に、友人関係です。私自身の経験でも、友達との遊びを通じて、喜んだり、悲しんだり、傷ついたり、傷つけあったりしながら、様々な対人関係上のスキルを、知らず知らずのうちに学んできたように思います。
しかし、今、子どもたちの遊びの環境が劇的に変化しています。遊び場自体が減っていると共に、公園やグラウンド等でも、友達と群れながら遊んでいる子どもは、私たちの子ども時代と比較して、びっくりするほど少なくなっています。子どもの生活が忙しくなっていることや、外で遊ぶことが危険になってきているという点も関係しているでしょうが、ゲームの存在も大変大きな役割を果たしています。今でも、小学校時代は友達の家を訪問しあって遊ぶ問うことが珍しくありませんが、多くの場合、一緒に何かをするというわけではなく、各自がゲームをしたり、漫画を読んだりするだけで、互いにコミュニケーションをとることは少なくなっています。
先日、医療少年院の法務官の話を聞く機会があったのですが、「今の子どもたちは未熟化していると言われているが、子ども時代に子どもらしい生活を送ることができなければ、逆に、幼児性が溜まってしまう。満たされない欲求が残り続けることになる。子どもは、友達等との遊びを通じて、自然に大人になっていくもの」と話されていました。今の子どもを取り巻く環境は、子どもが自然に大人になっていくことが本当に難しい環境になっていると思います。
もちろん、ゲームだけでなく、携帯電話やメールの存在も、子どもたちが直接会話する機会を失わせている点で、コミュニケーション能力の低下に大きく影響していると思います。もう半年くらい前になりますが、夜10時ころにファミリーレストランで食事を取っていると、隣の席に、塾帰りと思われる中学生3年くらいの4人の子どもが座っていました。私は30分くらい居たのですが、その間、その子たちは、それぞれが携帯電話の操作に没頭し、結局、一度も互いに言葉を交わすことがありませんでした。メールをしているか、ゲームをしていたのだと思いますが、ひょっとすると、4人でメールで会話しているのではないかと思えるほど、異様な感じがしました。しかし、柳田氏の本でも触れられているのですが、このような光景は決して珍しいものではなくなっています。子どもたちに限らず、大人が電車の中でメールに没頭する姿を見ても、私自身、あまり不自然にも感じなくなっています。
ゲームやネットの存在は、子どもたちを生の人間関係から遠ざけ、大変狭い世界に閉じ込めてしまう危険性を持っています。人間関係に煩わしさを感じたとき、傷ついた時、特に、引きこもり傾向を持ち始めた子どもたちにとって、自分一人で楽しむことができ、また、匿名性の中でコミュニケーションできるゲームやネットは、大きな逃げ込みの場所となっています。もちろん、一つの居場所としての意義は否定しませんが、そこにどっぷりとはまってしまうと、その狭い世界から抜け出ることが困難となります。また、本当に、バーチャルな世界と現実世界の区別がつかなくなってしまうなどの危険性があります。佐世保事件や寝屋川事件などの最近の重大事件には、その傾向がはっきりと出ています。3月頃の新聞で、「人間は死んでも生き返ることができる」と答える中学生が10%以上に上っているとの調査結果が報道されていました。信じられないような調査結果ですが、子どもたちが日常的に経験し、学びの場となっている世界が、それほど非現実的なものになってきているのです。
先日、私が学校評議員をしている高校で携帯電話の使用状況に関する調査が行われたのですが、その中にも、大変不安になる子どもたちの声がありました。質問の最後に携帯電話に関する要望を尋ねたところ、「風呂場でも使える携帯が欲しい」という意見がいくつか出たのです。皆さん、これはどういう趣旨だと思いますか?「濡れても使える携帯が欲しい」という単純な希望のような気もしますが、実はそうではありません。「今の高校生の間では、携帯メールが届いた時には、数分以内に返信をしないと、『冷たい』とから、『大切にしていない』とみなされる」という不文律があって、「風呂に入っている間にメールが来るのが一番心配だから、風呂場でも使える携帯電話が欲しい」というのが、その理由なのです。ここでも、子どもたちのナイーブというか、しんどい友人関係が見えてきます。このような気遣いの多い人間関係に拍車をかけているのが携帯電話•メールです。
柳田氏も指摘していますが、手紙でのやり取りには時間がかかります。そこには自分で落ち着いて考え、また、感情をコントロールする時間的余裕が自然に生まれます。また、家庭電話でのやり取りにも、同様に限界があります。しかし、携帯電話、特にメールでのやり取りには即応性があり、受け取ったものは、すぐに反応することが可能であり、感覚的にも、それを求められます。送った側もそれを期待します。結果として、自分の中で落ち着いて考えたり、感情をコントロールしたりすることなく、反応してしまうことが少なくありません。メールでのやり取りが、未熟なやり取りに終始したり、時にエスカレートしてしまうのは、相手の姿や雰囲気がわからないことと同時に、このような即応性に原因があると思われます。このような携帯電話•メールの特徴も、子どもたちの発達の機会を奪い、また、人間関係を気遣いの多いものにする原因になっていると思います。
ゲームや携帯電話、メール、インターネットが子どもたちの生活の中心をなしてきている今の状況は、本当に危険な状況であるという気がしてなりません。まさに脳の発達自体に大きな影響を与え始めているように感じます。何か手をうたないといけないと思うのですが、皆さんどうでしょうか?
しかし、ふと気がつくと、私も携帯を握りながら歩き、携帯が見当たらないと不安になってしまいます。私自身も、携帯依存症の一歩手前のようです。
 壊れる日本人―ケータイ•ネット依存症への告別
壊れる日本人―ケータイ•ネット依存症への告別
柳田邦男(著) / 新潮社 / 2007年10月30日
<内容>
残忍な少年犯罪の続発、効率優先が引き起した重大事故、相次ぐ企業の不祥事――この国は本当におかしくなってしまったのか? 急激なIT化が私たちから奪ったものを徹底検証し、曖昧な故に芳醇だった日本文化再生を訴える。便利さを追求すれば必ず失うものがある。少し不便でも、本当に大事なものを手放さない賢い選択をしよう。ちょっとだけ非効率な生き方を提唱する警世の書。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。