門前追悼
23回目の朝
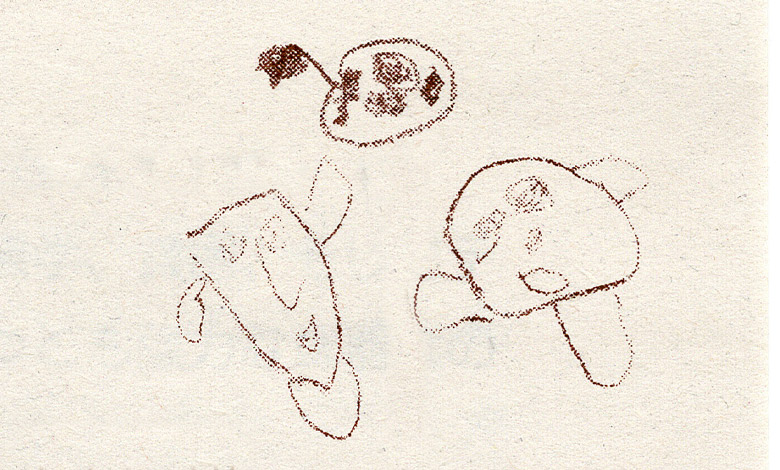
所薫子
今年は土曜日。7時30分頃に着くと既に花は届いていて、クラブ活動の学生が閉まっている門扉の前に立っていました。時計台の時計は壊れて止まったままになっていました。
毎年23年間、1回も欠かさず東京から来て下さっている中村羅針さんが今年もみえました。路上で石田僚子さんのことを語り、唄い、いくらかずつ貰ったお金を1年間貯めてカーネーションを買って、車に積んで来られていました。最初の年は1年間で30万円。9年間で一万本の花を供えられました。
19年目に2万本。羅針さんお一人で、去年までに24,000本のカーネーションを供えられました。私たちの中でさえ風化している今、路上で知る人も無い中で、語り伝えていく。私にはとてもできません。
事件当時、石田僚子さんは遅刻常習犯だったとか不良だったとか根も葉もない噂が広がり、中学生の弟が通学中に取材攻勢に遭うとか、越して来たばかりの家を越さなくてはならなくなりました。殺されただけでなく、二重にも三重にも被害に遭われました。
学校へ入ろうとする学生を教師の押した鉄の扉で殺害してしまったこと。
また事件現場に流れた血を水で流し消し去ってしまったことを「教育的配慮」としてしまったこと。諸々の証拠隠滅、当時の学生たちに事実を伝えなかったこと、事実と対面させなかったことも「校長の裁量内」としてしまったこと。毎年、毎年、動ける間はこのことを伝えていかなければなりません。わたしたち人間は、とんでもない間違いをする動物であることを忘れないように毎日を過ごしたいものです。






